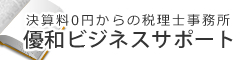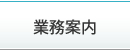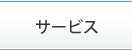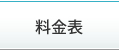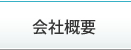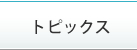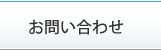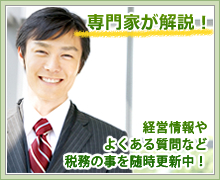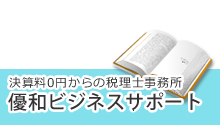2015,12,01, Tuesday
相続財産で金額が大きくなるものの代表的なものに、不動産、株式、預貯金などがあげられます。
中でも株式については、実際手許にそれだけの財産が残るというものではなく、相続したという
実感に欠けます。
会社との関係もあり、業績等により金額に大きく変動が生じます。特に毎年利益が出ているような
会社ですと、株価はどんどん上がっていきます。
会社の状況により事業承継を考える必要があり、計画的に進めることが相続対策になります。
非上場株式についての優遇税制に納税猶予があります。この納税猶予は、贈与と相続があり、
条件が合えば非常に有利になります。
贈与税については、一定の要件範囲内であれば贈与税の全額が猶予されます。
また、相続税については非上場株式の価格の80%に対応する相続税が猶予されます。
平成27年の贈与税の納税猶予については、経済産業大臣の認定が必要です。
申請期限は平成27年10月15日から平成28年1月15日までとなっているため、ご興味のある方は
早めにご相談下さい。
事業承継という大変大切な問題であるため、一人で考えず一緒に考えましょう。
詳細は税理士法人優和の最寄りの各本部までお問い合わせ下さい。
京都本部 中村真紀
2015,11,17, Tuesday
マイナンバーの配送が始まり、お手元に届いている方もいらっしゃるかと思います。
同時に企業には年末調整に関する資料が送付され、そろそろ年末に向けた業務の
準備をされているのではないでしょうか。
平成28年度分の扶養控除等申告書より、本人確認及びマイナンバーの確認を行う
こととなり、準備は例年以上に大変なものになっていることでしょう。
そうした中、平成27年度の税制改正大綱により日本国外に居住する親族に係る
扶養控除等の書類の添付等義務化がされました。
例えば、生計一親族(仕送りなど必要)で、年間の合計所得金額が38万円以下であれば、
例えその方が海外に住んでいても、日本で扶養控除の対象にすることは可能です。
そして、外国人でも日本国内の居住者であれば、日本の年末調整対象となります。
しかし、これまでは外国の扶養親族は日本の税務署ではその人数の正確な数を
把握することが困難で、それを逆手に取って扶養人数を実際以上に増やして扶養控除を
受けているという実態が散見されていました。
そこで、平成27年度税制改正では、【日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の
適用を受ける納税者に対して、確定申告書等に「納税者の親族であることを確認できる
書類」、「納税者が親族の生活費等に充てるための支払を行ったことを確認できる書類」を
添付し、又はその確定申告書等を提出する際に提示することを義務付ける】ことの一文が
追加されました。
上記の「親族関係書類」とは、次の1又は2のいずれかの書類となります。
1)戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類でその非居住者が
その居住者の親族であることを証するもの及びその親族の旅券の写し
2)外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、その非居住者がその居住者の
親族であることを証するもの(その親族の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る)
上記の「送金関係書類」とは、その年における次の1又は2の書類で、その非居住者である
親族の生活費又は教育費に充てるためのその居住者からの支払が、必要の都度行われたことを
明らかにするものとされています。
1)金融機関が行う為替取引によりその居住者からその親族へ向けた支払が行われたことを
明らかにする書類
2)いわゆるクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入した
こと及びその商品等の購入代金に相当する額をその居住者から受領したことを明らかにする
書類
人手不足の昨今、外国人労働者を雇用する機会も増えているかと思います。
ご不明点は、お気軽にお問合せください。
茨城本部 香川
2015,11,01, Sunday
ふるさと納税とは、地方自治体への寄付金を指します。
所得税及び個人住民税の控除が受けられるのですが、内容を下記記載します。
◎税制改正について
平成27年4月1日より税制改正が行われて、ふるさと納税が更に利用しやすくなりました。
◆控除額が2倍になりました。
個人住民税の特例控除額を計算する上での限度額が個人住民税所得割額の1割から2割に拡充されました。
◆確定申告が不要になりました。
年間に5自治体までの寄付であれば、ふるさと納税ワンストップ特例制度により確定申告が不要になりました。
次に、所得税と個人住民税の税額控除額を記載します。
※所得税
所得控除額=寄付金額-2,000円
つまり、所得税の軽減効果としては「所得控除額×所得税の限界税率」となります。
※個人住民税
1)基本控除額
(寄付金額-2千円)×10%
2)特例控除額
(寄付金額-2千円)×(90%-所得税の限界税率)
但し個人住民税所得割額の2割を限度
所得税の限界税率とは、所得税の税額計算の際に適用された税率のことです。
所得税の税率は、課税所得に応じて5%~45%まで区分されています。
例えば、年収500万円の方(所得税の限界税率10%と仮定)がふるさと納税を52,000円したと仮定すると↓↓
① 所得税
(52,000円-2,000円)×10%=5,000円の所得税額控除となります。
② 住民税(基本控除額)
(52,000円-2,000円)×10%=5,000円の住民税額控除となります。
③ 住民税(特例控除額)
(52,000円-2,000円)×(90%-10%)=40,000円の住民税額控除となります。
結論として、
所得税5,000円+個人住民税45,000円=50,000円の税額控除となり、実質2,000円の負担でふるさと納税が出来ます。
特産品などの特典も沢山ありますので、試しに利用されてはいかがでしょうか?
茨城本部 楢原英治
2015,10,15, Thursday
平成28年1月1日より、公社債及び株式等に係る所得に対する課税が大幅に改正されます。
(1)公社債等の利子所得及び譲渡所得等の改正
国債、地方債、外国国債、外国地方債等の利子所得について源泉分離課税から申告分離課税へ
課税方式が変わります。
更に上記国債等は、譲渡所得については非課税でしたが、改正後は20%(所得税15%、
住民税5%)の申告分離課税となります。
(このようなことから最近、証券会社等で今年中に国債を償還して、来年からはNISAで
再度国債を購入しましょうなどという案内が出されているようです。)
(2)上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算並びに繰り越し控除の改正
上場株式等の譲渡損失及び配当所得等の損益通算の特例の対象範囲に上記の利子所得等
及び譲渡所得等が加わります。
ここで大きく影響を受けそうなものが、外国国債等で格付けの高い安全な金融商品で運用が
なされている外貨建MMF(マネー・マーケット・ファンド)でしょう。
(MRF:マネー・リザーブ・ファンド)と間違えやすいのでご注意ください。)
ここ数年の為替の変動により、外貨建MMFを保有されている方の中には多額の含み損益を
発生されているのではないでしょうか。
含み損が出ている方は、今年中の売却は絶対に避けるべきでしょう。
というのも今年中の売買については損が出ても非課税で他の譲渡所得とも損益通算
できませんので、来年以降損益通算が可能になってからの売却をお勧めします。
厄介なのが含み益のある方でしょう。
今年中に売却すれば含み益は非課税で来年以降は、20%の課税となりますので、
確かに今年中に売却すれば税金はかかりませんが、今後何かのきっかけで大幅な円安になる
可能性もありますし、この先の為替の動向を注視しながら検討する必要がありそうです。
(個人的には今年中に一旦利益を確定し、場合によっては来期以降に再度トライすることを
お勧めしますが・・・)
(3)株式等に係る譲渡所得等分離課税の改正
これまでは、一般株式等(非上場株式などがこれに該当します)と上場株式等の損益通算が
可能でしたが、今回の改正で来年より一般株式等と上場株式等が分離課税の中でさらに
分離されて別のカテゴリーとなり、非上場株式と上場株式の損益通算ができなくなります。
もしすでに今年に入って非上場株式の譲渡があり、そのほかに上場株を保有されているの
ならば、損得ともに損益通算できる最後のチャンスです。
以上、今年も早いもので残り2か月余りですが、そろそろ「ファイナルアンサー」ですね。
埼玉本部 菅 琢嗣
2015,09,15, Tuesday
平成27年度税制改正により、電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線
(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と
位置付け、その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するか否かの
判定基準が、役務の提供を行う者の事務所等の所在地から「役務の提供を受ける者の
住所地等」に見直されることになりました。平成27年10月1日から施行されます。
この結果、電気通信利用役務の提供について、従来課税対象取引とされていた国内
事業者が行う海外事業者・国外消費者への当該役務提供取引は課税対象外取引となり、
従来課税対象外取引とされていた国外事業者が行う国内事業者・国内消費者への当該
役務提供取引は
課税対象取引となります。
そして、電気通信利用役務の提供については、当該役務の提供を受けた国内事業者に
申告納税義務を課す方式(リバースチャージ方式)が採用されます。消費税は本来資産の
譲渡等を行った事業者が納付する仕組みとされていましたが、このリバースチャージ方式
は課税仕入れを行った事業者が申告納付する仕組みとされています。
また、平成28年4月1日からは、特定役務の提供(国外事業者が行う映画等の俳優,芸能人
または職業運動家の役務提供を主たる内容とする事業として行う役務提供の内、国内の事
業者に対して行うもの)についてもリバースチャージ方式が導入されます。
事業者向け気通信役務の提供及び特定役務の提供を特定課税仕入れとして、原則特定課税
仕入れを行った事業者に納税義務が課せられるリバースチャージ方式とされていますが、課税
期間の課税売上割合が95%以上である場合には特定課税仕入れはなかったものとされる
経過措置が設けられており、この場合には課税対象外取引として取り扱うこととなります。
東京本部 小林
2015,09,01, Tuesday
平成26年4月より消費税が8%となり、納税額が3%分多くなりました。
また、景気が少々上向いた(?)ことにより、売上が多少回復したので、
その分納付税額が大幅に増えた会社は多くあります。
もちろん消費税は預かった消費税から支払った消費税を引いた差額ですので、
納税には支障を生じないはずですが、実際には納税に苦慮している会社は、多いはずです。
平成26年の税制改正により、分納(換価の猶予)の申請制度が平成27年4月に
創設されました。
以前は申請ではなく税務署側の職権で分納が許可されていましたが、ほとんどの事業者が
滞納しているか、換価(差し押さえ等)通知により、税務署へ相談にいくケースが多かったようです。
この場合、税務署の職権ですので時間もかかり、かつ、延滞税の負担が大きかったようです。
また、職権ですので、分納を認められなかった場合でも不服申し立てはできませんでした。
今まで納税の延滞がなかった場合には、1年間の分納が認められ、かつ、延滞税の軽減
(1.9%)もスムーズにいくようです。
ちなみに平成27年の国税の通常の延滞税は、2か月まで2.8%、以後9.1%です。
ただし、申請には分納計画、財産目録、過去一年の収支計算明細、収支見込み、
他の国税等の納付予定状況等を記載しなければなりません。
分納をされる方は、早めにご準備をしてください。
東京本部 市川
2015,06,01, Monday
先日このようなケースがありました。
とあるマンションを母が3/15、長男、二男、三男がそれぞれ4/15を共有で持っていました。
その後母が亡くなり、母が遺した遺言書には「101号室と102号室は長男が201号室と
202号室は二男が301号室と302号室は三男がそれぞれ取得することを前提に区分登記して、
私(母)の持分3/15を3人で1/15ずつ相続してください。その後各々の持分が1/3となった
段階で3人が取得する部屋ごとに交換してください。」といった内容のものでした。
このようなケースであれば、兄弟で交換するのでなく共有物分割を行うべきでしょう。
共有物分割とは共有している不動産等の共有状態を解消し土地なら分筆、
建物なら区分所有といった形で所有することを言います。
交換と共有物分割、最終的な取得形態は変わりませんが、例えば不動産取得税ですと、
交換の場合AがBの土地を、BがAと土地をそれぞれ取得したものとみなされ、不動産
取得税の課税対象となりますが、共有物分割の場合、不動産取得税はかかりません。
更に登録免許税については、交換の場合は固定資産税評価額の2%かかるのに対し、
共有物分割の場合0.4%で済みます。
ダメ押しで税務においては、交換特例は保有期間が1年以上だとか使用用途が同じで
あるとか交換資産の価額差が高い方の価額の20%以内でなければならない等々、
非常に厄介な「シバリ」が多く我々実務家としても悩ましい特例であるのに対し、
共有物分割の場合、土地の譲渡はなかったものとみなされ、譲渡所得税などの
課税関係は生じません。
このようにいいことばかりの共有物分割ですが、注意も必要です。
例えば、AとBが1000㎡の土地を1/2ずつ共有で持っていたとして、これを分筆して
500㎡ずつとし、共有物分割登記をした場合には一見問題ないように思われますが、
片方の土地は主要道路に面した角地で、もう片方はその奥にあり、時価が主要道路側
の方が倍近いケースも想定されます。
この様に持分比率が持分に応じていない分割も考えられ、持分比率の低いほうから
高い方への贈与があったとみなされ、贈与税が課税されることとなり、額によりますが
ほとんどのケースは譲渡による所得税よりも高い税率となることとなるでしょう。
不動産取得税や登録免許税にしても共有物分割とみなされず、交換と同様の課税となります。
時価比率と持分比率は「おおむね」一致していることが条件ですが、安易に考えると
余計に税金がかかることもありますので、くれぐれもご注意下さい。
埼玉本部 菅 琢嗣
2015,03,16, Monday
2015年1月から相続税は税率の見直しや基礎控除引下げによる増税がスタートしています。
一方で、贈与税については緩和措置が講じられています。
その中に、少子高齢化の進展・人口減少への対応として創設される「結婚・子育て資金の一
括贈与に係る贈与税の非課税措置」があります。
これは、2015年4月1日から2019年3月31日までの間、結婚や子育ての支払いに充てる
ために直系尊属から金融機関に信託等される金銭等について、受贈者1人につき1000万円
(結婚関連は300万円)まで贈与税を非課税にするものです。
従来から生活費や教育費に充てるために扶養義務者から必要な都度受ける贈与は
非課税扱いとされているのですが、使途を限定してまとまった金額を動かせるようにすることで
富裕層が抱える資産を動かしつつ、結婚や子育てのフォローをより手厚くする狙いがあります。
また、2013年度税制改正で創設された「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の
贈与税の非課税措置」についても緩和されます。
この制度は、祖父母や祖父<直径尊属)から30歳未満の子や孫(直系卑属)に対する教育資金
の支出について、子や孫1人あたり1500万円まで贈与税を課さないというもので、子や孫名義
の金融機関口座に教育目的の資金をまとめて信託等することが条件となります。
2015年度税制改正では、同制度の対象となる教育資金の範囲に、「通学定期代」や「留学
渡航費」等が追加されます。
更に、金融機関へ提出する領収書等に記載された支払金額が1万円以下で、かつその年中
の合計支払金額が24万円までのものは、その領収書等に代えて支払先、支払金額等の明細
を記載した書類を提出できるとの見直しを行った上で、その適用期限が2019年3月31日まで
延長されることになりました。
相続税の増税が行われた分、こうした緩和措置を上手に利用していきたいものですね。
茨城本部 香川
2015,01,15, Thursday
平成27年度税制改正大綱においては、課税ベースの拡大等により財源を確保しつつ
税率を引き下げ、経済の好循環の実現を力強く後押し、成長につながっていくように
法人課税の改革を行うとされています。
この法人課税の改革として、法人課税の改革に係る改正案が挙げられており、
その中に、下記の法人税率の引き下げと中小法人の軽減税率の特例の延長があります。
法人税の税率が、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、23.9%(現行25.5%)に
引き下げられます。
また、中小法人の軽減税率の特例(所得のうち年800万円以下の部分に対する
税率:19%→15%)の適用期限が2年延長され、平成29年3月31日以前に開始する事業年度
まで適用されます。
ここでいう中小法人とは、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の普通法人のうち、
資本金の額もしくは出資金の額が5億円以上の法人等の100%子法人等を除く法人を
いいます。
ちなみに、法人税率等が税法の改正により変更され、改正税法が当期の決算日以前に
公布されている場合、当期の税効果会計において適用する将来の税率は改正後の税率
を適用することになりますのでご留意ください。
東京本部 小林歩
2015,01,05, Monday
平成27年が幕を開けました。
例年ならば、お正月休暇前に政権与党の税制改正大綱が発表されていますが、
本年はアベノミクス解散により仕事納めの後、12月30日に発表となりました。
平成27年は、既に平成25年に改正されて相続税の改正が施行になります。
基礎控除の見直し、税率構造の変更等、具体的には配偶者、子2人で
今まで8千万円でしたが、改正により4千8百万円と減額されています。
相続税の最高税率が50%から55%へ引き上げられました。
さて、年末に発表された税制大綱では、法人税の実効税率の引き下げや、
高齢者から若年層への資産の移転を促進するため住宅取得資金の贈与の
非課税枠の拡大、未成年者版NISA制度の創設、教育資金の贈与税の
非課税制度の延長等があります。
住宅取得資金の贈与は、現行500万円(エコ住宅1000万円)から
1000万円(エコ住宅1500万円)へ拡充されます。
未成年者のNISA口座では80万円の非課税枠が創設されます。
税制をご利用される方、節税対策をされる方は、自己判断をせず
専門家(税理士)へご相談ください。(もちろん当法人へ)
東京本部 市川多余