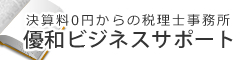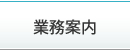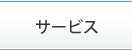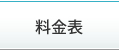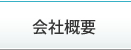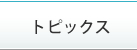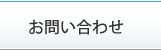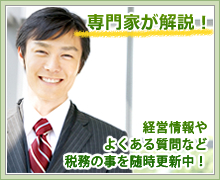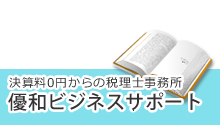2017,07,01, Saturday
一定規模以上の社会福祉法人や医療法人について、公認会計士による監査が導入されることとなりました。公認会計士監査を導入することによって、計算書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することが第一に求められています。
そして、結果として社会福祉法人や医療法人のガバナンスの強化、透明性の向上といった経営力の強化に資することが期待されています。
多額の税金が投下されて運営されている点を鑑みれば、全ての社会福祉法人及び医療法人に関して監査が必要とも言えますが、小規模法人の監査負担などを考慮して、一定規模の法人が対象となっています。今回は社会福祉法人に限定して要件などを記載します。
★一定の事業規模とは
最終的には、収益(事業活動計算書におけるサービス活動収益)が10億円以上の法人又は負債(貸借対照表における負債)が20億円以上の法人が対象となります。
ただし、社会福祉法人に規模に応じ、監査を段階導入することとされました。
◎H29・H30年度→収益30億円超又は負債60億円超
◎H31・H32年度→収益20億円超又は負債40億円超
◎H33年度以降は、収益10億円超又は負債20億円超
となります。
★監査の内容について
監査の具体的な内容についてですが、大まかに言えば、会社内部のルールがキッチリしていて、決めたルールが守られているかを確認されます。そして、法人を代表する役員の方々の誠実性や考え方についても経営者インタビュー等で確認されます。
ざっくり言えば、経営者が真面目で不適切な支出や不正をしない方かを確認してリスクを把握します。経営者の誠実性はなによりも重要な項目です。
その他、固定資産を購入する場合や給与決定・支払いなどの手続きに関する承認ルールが適切に決まっているか、決まったルールが適切に運用されているかを確認します。実際にサンプリングして書類の確認も行われます。
例えば、総勘定元帳から固定資産の取得仕訳を抽出し、適切な承認手続きが踏まれているかを確認します。
上場企業であれば、毎期監査を受けているので慣れていると思いますが、今回は非上場企業に対する法定監査になりますので初年度は双方に戸惑う部分があるかと思います。
会社のご担当者も、何故その手続きが必要なのか疑問がある場合には、適時に質問して手続きの必要性を理解して監査を受けることが有用だと思います。
最後に、
梅雨時期でじめじめした日が続いておりますが、元気ハツラツで前向きに頑張っていきましょう♪♪
本ブログがお読みいただいた方の参考に少しでもなれば嬉しいです。
茨城本部 楢原 英治
2017,06,15, Thursday
「こんなに交際費使っちゃったら税務署から睨まれますかねぇ・・・」顧問先の社長さんとの間で
こんな会話があったとします。
この会話での「税務署に睨まれる」ということの本当の意味はどういうことなのでしょうか。
きっと税務調査が入って、その行き過ぎた交際費支出が否認されるといったところなのでしょうが、
そこまで行き着く過程はもっと奥の深いものであったりします。
そもそも課税庁側が否認をするには、何らかの根拠をもって否認することになりますが、
その根拠というのは国税庁通達であることが一般的なのでしょう。
ただし、国税庁通達は納税者を拘束するものではないことから、納税者側としてはそれに対して
反論をしていくことになるのですが、その時の反論根拠は場合によっては国税庁通達における
解釈の相違や過去における判例、裁決事例などを反論根拠としていくことになるのでしょう。
ここで、税務における判決と裁決の違いについて簡単に説明しますと、「判決」とは裁判所
としての税法解釈であり、「裁決」とは国税不服審判所が示した税法解釈なのです。
上記のように、税法解釈の相違があった場合に納税者側は課税庁側からの指摘事項に関して
修正申告に応じなければ、課税庁側は「更正処分」を行います。
その処分に納得がいなかない場合、いきなり裁判所に訴訟の提起をするとなると全国各地で
膨大なる税務訴訟が行われ混乱をきたすことから、まずは国税不服審判所へ異議申立てをし、
そこで国税不服審判所の税法解釈であるいわゆる「裁決」が示され、それにも納得がいかない
場合に初めて税務訴訟が提起され、その後は地裁で不服申立てとなると高裁へ控訴し、
さらには最高裁へ上告し、最終的な税法解釈いわゆる「判決」が確定します。
税務上の見解の相違については、過去に類似した「裁決」や「判決」の事例が集まった
「裁決事例」や「判例・裁判例」を反論根拠としますが、その中でも最終的なジャッジである
最高裁での判決が最も強い反論力があります。
課税庁側と納税者側の見解の相違におけるせめぎ合いも、最高裁での判例を持ち出された
時点で勝負ありなのです。
これら判例や裁決事例は、法律として明記されていながら「法」として事実上納税者を
拘束することができる、いわゆる「不文法」であり税務の実務においては法と同様の拘束力が
あります。
当然のことながら、もし最高裁で納税者側の主張が勝った場合、すぐに国税庁通達が変わると
いったこともよくあり、最近では財産評価基本通達の一部が改正となった最高裁の判決などは
記憶に新しいところです。
ただし、税務訴訟において納税者側の勝利する確率は低く、敗北後の延滞税等の追徴課税を
考えるとどこかで「落としどころ」を模索していかなければならないのも事実なのかもしれません。
本来は税務判断における見解の相違も修正申告に応じるかそうでないかも、そこまで考慮して
から判断すべきなのでしょう。
埼玉本部 菅 琢嗣
2017,06,01, Thursday
よく税務における会話で「今度税法が変わりまして・・・」とか「税法ではこの様に解釈しておりまして・・・」などと言ったりしますが、実のところそれは「税法」が変わったのでなくて「通達」が変わったにもかかわらず、そのような表現をしてしまっていることが多いのではないでしょうか。(私自身も身に覚えがあります・・・)
「通達」とは、国税で言うところの国税庁長官が国税局や税務署及びその職員に対して法令の解釈や実務運営指針を伝える文書のことを言い、法令と違い国民(納税者)を拘束するものではありません。
ただし、これらは課税庁側の勝手な論理において決められたものではなく、過去における判例や裁決などをもとに税法の専門家などが協議立案し国会の審議を踏まえ全国統一で一律の見解が示されたものなのです。
そのようなことから税の実務においてもあたかも法令と同様であるかのように扱われているのもまた事実なのかも知れません。
それでは、通達に従った解釈がすべて正しいかというとそうとも限らず、例えば財産評価基本通達における時価評価に関しても昨今、金融機関等主導と思しき租税回避スキームが横行しており、確かに通達を形式的、機械的に解釈するならばその通りなのかもしれないものであっても、課税庁側はその行為があまりにもあからさまに租税回避行為と疑われる事案については、「財産評価基本通達第1章総則6項この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」いわゆる「総則6項」を適用して通達とは別の評価額をもって否認することもあります。
また、納税者側の立場で通達に従った解釈をすることが本来あるべき「時価」とかけ離れた評価なのではと疑われるいわゆる「通達評価がなじまない事案」については、鑑定評価等の方法をもって本来あるべき「時価」を立証していくことも必要なのでしょう。
このように通達は法令ではありませんが、我々が税務判断を行う上でかなり重要な判断基準であることは間違いないのですが、常に「通達は絶対的ではないという意識」を持ちつつ、適切な解釈判断を心掛ける必要があるのではないでしょうか。
埼玉本部 菅 琢嗣
2017,05,15, Monday
国、地方公共団体や公共・公益法人等は、本来、市場経済の法則が成り立たない事業を
行っていることが多く、通常は租税、補助金、会費、寄付金等の対価性のない収入を
恒常的な財源としている実態があります。
このような対価性のない収入によって賄われる課税仕入れ等は、課税売上げのコストを構成しない、
いわば最終消費者的な性格を持つものと考えられます。
また、消費税法における仕入税額控除制度は、税の累積を排除するためのものですから、
対価性のない収入を原資とする課税仕入れ等に係る税額を課税売上げに係る消費税の額から
控除することは合理性がありません。
そこで、国、地方公共団体や公共・公益法人等については、通常の方法により計算される
仕入控除税額について調整を行い、補助金等の対価性のない収入(特定収入)により賄われる
課税仕入れ等に係る税額について、仕入税額控除の対象から除外することとされています。
特例計算の対象となる事業者は、次のとおりです。
① 国の特別会計
② 地方公共団体の特別会計
③ 消費税法別表第三に掲げる法人
④ 人格のない社団等
ただし、次に掲げる場合には、仕入控除税額の調整を行う必要はありません。
① その課税期間の仕入控除税額を簡易課税制度を適用して計算する場合
② その課税期間における特定収入割合が5%以下である場合
ここで、特定収入割合とは、その課税期間における資産の譲渡等の対価の額(税抜き)の合計額に
その課税期間の特定収入の額の合計額を加算した金額のうちにその特定収入の額の合計額を
占める割合をいいます。
仕入控除税額の調整を行う必要がある場合、原則的な方法により計算される課税仕入れ等の
税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の額を控除した後の金額を仕入控除税額とします。
このように、国、地方公共団体や公共・公益法人等については、その他の民間企業等と異なる
仕入控除税額の計算が必要となる場合があるため、注意する必要があります。
東京本部 小林
2017,04,14, Friday
平成28年度補正「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」いわゆる、ものづくり補助金の
採択結果が出ました。
平成28年11月14日から平成29年1月17日まで公募を行い、全国で15,547件の申請があり、6,157件が
採択されました。(採択率は39.6%)
税理士法人優和 京都本部では、認定支援機関として6件の申請支援を行いました。
支援結果は次のとおりです。
都道府県 京都府 大阪府 滋賀県 合計
支援件数 4件 1件 1件 6件
採 択 数 4件 0件 0件 4件
採 択 率 100% 0% 0% 66%
京都地域におきましては、前年以前からの実績から採択率100%という実績を確保できたものの、
近隣他府県では採択を勝ち取ることができませんでした。
しかし、全国平均の約1.6倍の採択率は全国の認定支援機関の中でもトップクラスの実績です。
また、今回の支援実績をふまえ、次回に向けた近隣他府県対策も万全の体制で取り組むことが
出来そうです。
平成28年度の二次公募や平成29年度のものづくり補助金の有無は分かりませんが、本補助金又は
類似する補助金は今後も見込めると思われます。
税理士法人優和では、税務顧問サービスだけに留まらず、組織経営を活かした税務ソリューション
サービスを展開する全国でも数少ない税理士法人です。
当然に京都本部での実績は東京・埼玉・茨城の各本部と情報を共有しているため、関東エリアでの
対応も可能です。
認定支援機関はぜひ、税理士法人優和にご相談下さい。
京都本部 太田芳樹
2017,02,15, Wednesday
税法においては取引相場のない、いわゆる非上場株式の評価額を決定するということは
厄介な問題の一つであります。
というのも会社の株主構成や相続贈与等の状況によって評価方法が全く変わってしまうことも
有り得るからです。
その典型的な評価方法に配当還元評価方式という評価方法があります。
その詳細は割愛しますが、要はその株式を手にしても持ち株割合(厳密にいうと議決権割合)が
低く会社経営に影響を及ぼすこともなく、ただ配当を得ることしか目的がない場合に通常の評価と
比べて低く評価されるというものです。
相続税や贈与税の税額を算定するにあたり税額を低く抑えることができるという意味において
とても有利な評価方法なのですが、ここで気をつけなくてはならないことの一つに「種類株式」の
存在があります。
持ち株割合を判定するためには、その「持ち株数」の割合で判定するのではなく「議決権数」の
割合で判定することとなります。
昨今の会社法においては、株主によって会社支配が目的の株主もいれば、配当が目的の株主も
いるという状況を鑑みて、同じ株式であっても議決権数に差をつけるということがよくあります。
同じ1株であっても配当を優先する場合は議決権がゼロのこともあるし、配当よりも会社経営に
重大な影響を及ぼしたい場合は、1株の議決権数が10だったり100だったりすることも考えられます。
そうなったときに持ち株数でその割合を判定してしまうと、評価額が通常低い配当還元方式だと
思ったものが、実は原則的評価方式だったということも十分にありえることなのでくれぐれも
気を付けたいところです。
種類株式には「拒否権付株式」俗に言う「黄金株」というものもあります。
これは株主総会の決議のほか、拒否権付株式の株主で構成する種類株主総会において
会社の決定事項である取締役、代表取締役の選任、解任のほか事業譲渡、合併、解散と
いったものを拒否する権限をもった株式であり、とても強大な権限を持った株式です。
最近よく耳にする某国大統領が発令する「大統領令」と何となく似ていると思ったのは私だけでは
ないのではないでしょうか。
ここで一つ注意が必要なこととして、種類株式の発行にあたっては一度現在発行されている株式を
会社が回収し種類株式として同数株式を再び付与することとなり、その時に取得原価から時価にて
譲渡があったということで時価が取得原価以上の場合、譲渡所得が発生することとなりますので、
くれぐれも気を付けたいところです。
埼玉本部 菅 琢嗣
2017,01,16, Monday
公益法人は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えては
ならないという制約を受けます。この制約のことを収支相償といいます。
収支相償は二段階で判断されます。まず第一段階として、各事業単位で収支を見ることになります。
第一段階において収入が費用を上回る場合には、その額はその事業の発展や受益者の範囲の
拡充に充てられるべきものであり、当該事業に係る特定費用準備資金として計画的に積み立てる
ことによって収支相償の基準を充たすものとなります。第二段階では、第一段階の収支相償を充たす
各公益目的事業に加え、必ずしも特定の事業に係る収支に含まれないものの、なお法人の
公益活動に属する収支も加味し、法人の公益活動全体の収支を見ることになります。
剰余金が生じた場合には、解消計画の説明等が必要となります。
東京本部 小林
2016,12,15, Thursday
今年も出ました「ものづくり補助金」
例年よりかなり早めの公募開始で、平成29年1月17日(火)が期限となっております。
年末年始をはさむこのスケジュールに、皆様まだまだ準備ができていない方もおられるのでは
と思います。
管轄する中央会の担当者の方も「まさか今年も予算がつくとは・・・・」と思うぐらい、
中小企業からのニーズがとても高い補助金のようです。
ただ、今年は予算額が大幅にダウン(前年の約25%ダウン)となりましたが、他の新しい補助金
などもあるので、ものづくり補助金の対象とならなかった方にもチャンスが広がるかと思います。
さらに今年は第四次産業革命型(前回のいわゆる「Iot」の発展型)に高い機能が要求され、
「AI」や「ロボット」といった細かな規定が設けられております。
また、賃上げによる割増要件などの新しい規定も設けられ、Iot、AI、ロボットでなくとも
一定の要件を満たせば最大で3,000万円までの引き上げが可能となります。
では、今年は誰もが3,000万円を狙うべきか・・・・・と言うと、実はそうでもないようです。
まず、「第四次産業革命型」
単純に設備と事業内容がこれに合致する方は、間違いなく3,000万円狙いだと思います。
気を付けるべきは、賃上げ要件による割増を狙う方
ここを狙う企業さんは従業員数が少ない方向けです。
ものづくり補助金は従業員が300人以下(製造業の場合)は対象となりますが、この賃上げ要件の
対象となる方は、最大で約31人となります。
この31人分の賃上げとなると、そのコスト増加額で補助金の割増額を超える可能性もあります。
以上の点から「第四次産業革命型」の対象とならない方で従業員数が一定以上の企業は、
「一般型の1,000万円」が狙い目ではないかと思います。
税理士法人優和では、認定支援機関として、皆様のものづくり補助金の申請支援にも力を
入れております。
ご興味の方は、ぜひ一度、税理士法人優和までお問い合わせ下さい。
京都本部 太田
2016,12,01, Thursday
相続対策として民事信託が注目されつつあります。
民事信託とは、自分の財産を信頼できる人に託し、特定の人のために予め定めた目的に従って、
管理・処分してもらう財産管理・財産承継の方法です。
この民事信託は、認知症対策として特に有効です。
相続対策の最中に認知症になってしまった場合、以後は相続対策が出来なくなってしまいます。
ところが民事信託を使えば認知症になった後でも不動産の売却や賃貸借契約などが行えます。
2025年には65歳以上の高齢者5人に1人が認知症になると計算されているようです。
認知症になってからでは遅いため、元気なうちに民事信託を検討してみてはいかがでしょうか。
京都本部 中村 真紀
2016,09,15, Thursday
平成28年3月に、「平成27年度 公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」が
公表されました。この中において、個別に掲げられた企業会計基準について、公益法人に
適用するか否かの検討結果が示されています。
<検討した企業会計基準>
1. 退職給付に関する会計基準
2. 金融商品に関する会計基準
3. リース取引に関する会計基準
4. 棚卸資産の評価に関する会計基準
5. 工事契約に関する会計基準
6. 資産除去債務に関する会計基準
7. 賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準
8. 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準
9. 固定資産の減損に関する会計基準
<結論>
・公益法人にも適用すべきと結論付けたもの
1,3,5,6,7
・現行の公益法人の基準をそのまま適用すべきと結論付けたもの
4, 9
・金融商品に関する会計基準については、従来から適用されているので20年基準でも適用する。
ただし、一部の注記については対象となる金融商品を限定する。
・会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準については、当該基準によらない会計処理も
公正妥当と認められる会計慣行ということができる。
以上の結論に基づく新たな措置は、平成28年4月1日以降に開始される事業年度から講じられる
べき(ただし、それ以前からの実施を妨げない)とされました。
このため、公益法人においては、決算時に慌てることが無いよう、事前に上記会計基準の適用に関する検討が必要になると考えられますのでご留意ください。
東京本部 小林歩