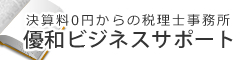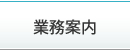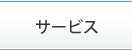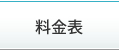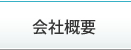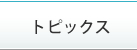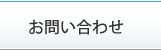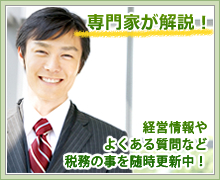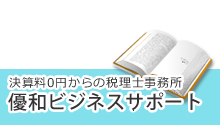2017,07,18, Tuesday
申告月になると、企業の中には消費税納付の時期にも関わらず、納税資金が不足しているため、
納付期限までに納付が出来ないというケースが希に見受けられます。
もちろん、消費税にかかわらず法人税等のケースもあり得るのですが、多くの場合、資金繰りに追われる企業は、赤字の場合がほとんどです。
赤字の場合、資金繰りが悪化していても法人税等は均等割りのみで良い場合が多いので、納付が遅れるという心配は少ないのですが、消費税の場合は赤字であっても何十万円の納付が必要なケースがでてきます。
そうなれば、この何十万円の納付ができず、税務署から差押え通知が来て経営者が驚愕するということもあります。
そうならないためにも、日常の資金繰りの管理をする際には消費税を考慮した資金繰りをする必要があります。
例えば、通帳残高が100万円で消費税の額が60万円あったとします。消費税を考慮しないと、経営者は使えるお金が100万円あると誤認し、その額を支払等に充ててしまったために、納付日に消費税を支払えないなんてこともあり得ます。
そこで、資金繰りを考える場合には、概算で消費税の額を見積り、その金額を控除する必要があります。
具体的には消費税の見積もり額(大きな変革がなければ概算で昨年の額と考えても良いでしょう)に相当する金額を別段預金にして、使わないようにする。
または1か月、2か月先の予想の資金繰り表を作成している場合には、予め消費税の納付額を除外して、今使えるお金は40万円であると強調するなどの方法があります。
このように、消費税のために資金がショートするのを防ぐためにも、事前に予想を立てて、今使えるお金がいくらなのかを把握することが大切だと考えられます。
茨城本部 大河原
2016,08,01, Monday
固定資産税(償却資産税)は、法人等が有する機械装置、工具器具備品などに対して
1.4%の税率が課されます。
赤字法人でも課されるため負担が生じます。例えば3,000万円の機械を取得した場合には、
年間42万円の償却資産税が課されます。
28年の改正により、中小企業者が取得する一定の機械装置については、この償却資産税の
半分が3年間減額されます。
上記の例により、3年間に納付する償却資産税の総額を1,008,000円(42万円 × 3年 ×
概算減価割合8割)とすると、その半分である504,000円が減額されることになります。
多額の投資をする際は、特に大きな減税となるため事前に検討しましょう。
この適用を受けるには認定計画に基づき取得することが要件になっているため、一度
税理士法人優和の最寄りの各本部までお問い合わせ下さい。
京都本部 中村 真紀
2016,06,15, Wednesday
実務において土地建物の売買契約書を目にする機会も多いのですが、中には土地と建物の
対価が契約書に区分されずに売買されているケースを見かけます。
これは実のところ少し厄介な問題が潜んでおり、当事者同士で土地建物それぞれの価額を
決定して契約書に記載していれば、税務申告をする側としてはその比率に従い粛々と申告
するだけなのですが、場合によってはその比率を税務申告する側主導の提案決定に委ねら
れることもよくあります。
例えば土地建物を購入した側とすれば、当然のこと建物の比率を多くしたいと考えます。
法人税・所得税では減価償却資産として経費となるし、消費税では仕入税額控除となるし、
売却した側とすればその逆を考えることでしょう。
そこで誤った比率の算定方法によって税務申告をする側が提案し採用してしまったとすると、
税務調査で否認され多額の追徴課税を納税者に課せられてしまうなどということもあり得ます。
実務の中でもこの土地建物の価額を割り出す方法はいくつかあり、それらの価額の決定方法
については納税者と課税庁が争う事例は多々ありますが、その中でも平成13年12月14日の
福岡地裁での判決はかなり合理的なもののように思えました。
結論から言うと、その価格の決定方法としては、特に中古物件の場合は土地建物の
固定資産税評価額による方法が合理的であるとのことです。
当然のことながらその価額は時価とはかい離したものであるのですが、今回問題となって
いるのはあくまで土地と建物の按分比率であることから、例えば財産評価基本通達をもとに
土地について国税庁が算出した路線価を、建物については地方公共団体が算出した固定
資産税評価額を基礎とした場合、算出機関算出時期がそれぞれ異なることから適正な
価額比率を割り出すのには必ずしも適当とは言えず、同一の公的機関が同一時期に合理
的な評価基準で評価した固定資産税評価額による価額比で按分する方法が最も合理的で
あるとされております。
もし税務申告をする側がこの比率をジャッジするのであれば、絶対とは言い切れませんが、
この方法が一番妥当なのではないでしょうか。
ちなみに土地と建物の按分が終わってもそれでおしまいではなく、今度は、建物の中で
更に建物にするか、建物附属設備にするかという問題があります。建物附属設備の方が
建物に比べて初年度から費用計上の額が多くなり、納税額も少なくなるということです。
これについても平成12年12月28日判決において建物と建物附属設備について明確な区分が
なされていない場合に建物にすべて含めて減価償却費を計算したとする課税庁側の主張は
採用されず、建物本体の取得価額を合理的な方法により建物本体及び建物附属設備に区
分する「必要がある」という判断がなされています。
区分しなければ税務上否認されることも当然ないのですが、区分する「必要がある」という
判決がでている以上、区分すれば税額も減るわけですから、「ざっくり30%を建物附属設備」
なんてことをせず、同業他社からその価額を見積もるといったひと手間かける必要はありそうです。
そもそもこのようなトラブルを未然に防ぐためには日頃から契約書には土地、建物、建物
附属設備の額を明記するようにアドバイスすることなのでしょうが・・・。
埼玉本部 菅 琢嗣
2016,05,09, Monday
消費税の10%増税に伴い、平成33年4月1日から適格請求書保存方式、いわゆるインボイス方式が
導入されます。
仕入れ税額控除の要件としては、現在は請求書等保存方式であり、平成29年4月1日から
区分記載請求書等保存方式となり、平成33年4月1日から適格請求書保存方式となります。
請求書等保存方式と区分記載請求書等保存方式との大きな違いは、請求書等保存方式では、
税込金額による記載が必要で、適用税率と税額の記載義務はありませんが、区分記載請求書等
保存方式では、軽減税率対象資産である旨を区分して明記すること、税率ごとに合計した
対価の額を記載することです。
区分記載請求書等保存方式と適格請求書保存方式との相違点は、適格請求書を発行できる
事業者は、適格請求書発行事業者として登録が必要となることです。
区分記載請求書等保存方式では、免税事業者から発行された請求書による仕入れ税額控除は
可能です。しかし免税事業者は、適格請求書発行事業者として登録はできません。
つまり免税事業はからの仕入れでは、仕入れ税額控除ができないことになります。
免税事業者は、適格請求書発行事業者になるためには課税事業者になることになります。
納税、資金繰り、取引先との関係等を考慮して、慎重に選択することが必要です。
東京本部 市川
2016,01,01, Friday
昨年末に平成28年度の税制改正大綱がまとまりました。
本年度は、何と言っても消費税の軽減税率がメインですが、その他の項目としては、
法人税実効税率も現行の34.62%から平成27年度に32.11%、さらに平成28年度は31.33%と
引き下げられます。
一方、生産性向上設備投資促進税制の廃止、建物付属設備の減価償却方法が定額法のみと
なるなど、償却費の拡大路線から一転して縮小路線への転換の兆しが見えつつあります。
また、地方税においては、外形標準課税の拡大があります。
対象法人は、資本金1億円超と変わらないのですが、所得割に係る税率を引き下げて、
付加価値割、資本割を拡大する、つまり黒字法人はその利益に係る税である所得割が低くなるが、
付加価値割、資本割といった利益とは違う税に対しては拡大するという、あまり儲けを出していない
会社には、いささか重荷となる税改正となっています。
さて、メインの消費税軽減税率では、「酒類及び外食を除く食品全般」と定期購読契約の新聞
(週2回以上発行)で決着しました。
平成25年の税制改正時にちらっと現れた新聞等に対する適用範囲の拡大がにわかに表れています。
今後その他の書籍にも拡大するとかしないとか。
食品全般でもミネラルウオーターは、8%だが、水道水は10%とか、水道水は生活用水全般に
使われるが、ミネラルウオーターは飲むだけという理屈だそうです。
(ただし、今後変更の可能性はあります)
今炭酸水をシャンプーの時に使用するのが頭皮にいいそうですが、これは...とこれからいろいろな
意見が飛び交いそうです。
東京本部 市川
2015,05,01, Friday
商品を輸出する場合には、輸出免税として我が国の消費税は、課されません。
また、非課税資産、例えば車いすの輸出、外国からの利息の受け取りなども
非課税資産の輸出等として、消費税は課されません。
この非課税資産の輸出等は、消費税納付税額の計算上、影響を及ぼします。
たとえば、外国の国債、社債などの運用をされている場合に、この外国で発行
された債権の利息が非課税資産の輸出等に該当します。
これがどのように消費税の計算に影響を与えるかと言いますと次の通りです。
消費税は、基本として預かった消費税から支払った消費税の差額を納付します。
ただし、課税売上割合が95%未満等の場合には、支払った消費税に課税売上
割合を乗じた金額が差し引かれます。
この課税売上割合とは、
課税売上
課税売上 + 非課税売上
仮に、売上が1千万円・消費税80万円・仕入5百万円・消費税40万円・非課税売上5百万円
とすると、課税売上割合以下となります。
1千万円
1千万円+5百万円
= 66.66%
納付税額は 80万円-40万円=40万円ではなく、80万円-(40万円×66.66%)=53万円
となります。
外国債権の利息を受け取った場合には、非課税資産の輸出等として上記の課税売上
割合の分母分子に加算されます。
たとえば、課税売上1千万円・非課税売上5百万円・非課税資産の輸出等5百万円とすると、
1千万円+5百万円
1千万円+5百万円+5百万円
=75%
となり、納付税額は、80万円-(40万円×75%)=50万円となります。
ただし、近年の複雑な金融商品が多種多様に存在します。
その中に外国で発行された債権の利息と判断するのは容易ではありません。
金融資産を購入した際には、非課税資産の輸出等にあたるものか否かを
金融機関等にご確認ください。
東京本部 市川 多余
2014,10,15, Wednesday
近年、個人住民税の特別徴収を徹底する自治体が増えてきております。
そもそも個人住民税は納税方法が所得税の源泉徴収と違い、個人が自身で納付する
「普通徴収」という制度が例外的に認められてきました。
例外的にと言いましたが、実際のところ従業員が数人程度の規模の事業所では、
概ね普通徴収で従業員が各々納税をしている事業所が多いのではないでしょうか。
ただ、やはり個人ごとに納税をまかせるとなると、滞納をしてしまう方も多くなってしまう
ということから、このように特別徴収を徹底する動きがでてきました。
埼玉県においては、今月に入り普通徴収を選択している従業員のいる事業所に
各市町村から一斉に特別徴収義務者の指定予告通知書が送付されました。
内容としては、下記のような場合のみ「普通徴収該当理由書」を提出することにより、
当面の間普通徴収が認められるとのことです。
(普通徴収が認められる条件)
・総従業員数が2人以下の事業所
・他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者)
・給与が毎月支給されていない方(不定期受給)
・専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)
・退職された方又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の方
従って、従業員ほうから自分は今までも遅滞なく納税してきたし、今後も自身で納税する
という理由は通用しなくなり、特別徴収を上記の理由書なく放棄した場合は、
特別徴収義務者として指定された事業者が、従業員から徴収すべき税額を放棄又は
滞納したとみなされ、原則として納期限後20日以内に督促状が発送されます。
そしてそれでも納付されない場合は、事業者に対して滞納処分が行われることとなります。
当然そうなると従業員が納税証明書を取得できない等の不利益を被ることとなります。
細かい点だと、例えば納税額が市県民税の均等割りのみという方については、
最初の徴収月である6月にまとめて特別徴収することとなっておりますので、
この様な方まで特別徴収の対象となっております。また、従業員が10人未満
である事業者は、申請により市区町村の承認を受けることで、年12回の特別
徴収税額の納期を年2回とする納期の特例を受けることができます。
この場合、所得税のそれとは違い、6月から11月までの分については、
12月10日まで、12月から翌年5月までの分については、6月10日までに
それぞれ納入することができます。
以上、埼玉県では、平成27年度よりこのように実施されますが、全国的にはすでに
実施している自治体もあり、今後はそのような流れになることは避けられないことと
なりそうです。
埼玉本部 菅 琢嗣
2014,08,04, Monday
利益を出すにはどうすれば良いか? 答えは2つ。
売上(収益)を増やすこと。 もう一つは経費(費用)を減らすことです。
簡単なことに聞こえますが、なかなか難しいものです。
資本金が1億円以下で一定の法人は、年間800万円までの交際費について
全額損金に算入されます。以前は1割が損金に算入されませんでしたが、
交際費を使いやすくするような改正が行われました。
ここで先程の問題を考えてみましょう。交際費が使いやすくなったからと言って、
無駄に交際費を使いまくるといのは最悪ということは誰もがわかることです。
交際費を使う目的は売上の増加を目的として使う場合、売上の減少を防ぐために
使う場合が多いでしょう。
ではその交際費が、本当に売上増加等に貢献しているものなのでしょうか?
お歳暮お中元などで数年取引がない先に送り続けたりしていないか。
数年間行っていないゴルフ場やリゾートマンションの会費を払い続けたりしていないか。
1万円の利益を出すために2万円を使ったりしていないだろうかなどを検討する
必要があるでしょう。
もう一つ、利益を出すために経費を減らすのは良いことですが、本来使うべきところに
お金を使っていない会社が多いです。
交際費がゼロとういう会社も問題があると考えます。一席設けることにより仕事の機会が
増えるところ、少額のお金をけちることにより大きな機会損失となります。
経費を減らすことばかりでは、単なる縮小に繋がってしまします。逆に経費を増やすことにより
売上を増加させるといった拡大志向でありたいものです。
仕事が忙しく作業ばかりしている方は、是非一度キーマンとなるべき人に声掛けをして
交際費を使ってみるのも面白いですね。
京都本部 中村真紀
2014,07,15, Tuesday
簡易課税制度とは、事業者の基準期間(その課税期間の前々年又は前々事業年度)に
おける課税売上高が5,000万円以下で、その課税期間開始の日の前日までに『消費税
簡易課税制度選択届出書』を提出している場合に、実際の課税仕入れ等の税額を計算
することなく、課税売上高に対する税額の一定割合を仕入控除税額とする制度です。
この一定割合(みなし仕入率)は、卸売業(第一種事業)、小売業(第二種事業)、製造
業等(第三種事業)、その他の事業(第四種事業)及びサービス業等(第五種事業)の5
つに区分し、それぞれの区分ごとに定められています。
簡易課税制度は平成27年4月1日以後に開始する課税期間より改正が行われることと
なりました。
大きく変わるのは金融業・保険業及び不動産業で、現行の第四種事業のうち、金融業
及び保険業を第五種事業とし、そのみなし仕入率を現行の60%から50%とするととも
に、現行の第五種事業のうち、不動産業を新たに新設した第六種事業とし、そのみなし
仕入率を現行の50%から40%とすることとされました。
[みなし仕入率]
<現行>
第一種事業 卸売業 90%
第二種事業 小売業 80%
第三種事業 製造業等 70%
第四種事業 その他の事業 60%
第五種事業 サービス業等 50%
<改正後>
第一種事業 卸売業 90%
第二種事業 小売業 80%
第三種事業 製造業等 70%
第四種事業 その他の事業 60%
第五種事業 金融業及び保険業
サービス業等 50%
第六種事業 不動産業 40%(新設)
※保険業には、生命保険業や損害保険業の他、保険代理店が含まれます。
※不動産業には、不動産賃貸業、駐車場業、不動産管理業、土地建物売買業、不動産
仲介業が含まれます。
前述のとおり、この改正は平成27年4月1日以後に開始する課税期間より適用されますが、
この適用開始日に関しては、経過措置が設けられています。
消費税簡易課税制度選択届出書を提出していない事業者が平成26年9月30日までに
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すると、届出書の強制適用期間である2年間は
改正前のみなし仕入れ率が適用されることになります。
これに伴い、簡易課税制度を選択している会社は、簡易課税制度と本則のどちらが得かを
また検討しなおす必要が生じてくるかと思いますし、これから簡易課税制度の適用を行う会
社は、みなし仕入率の経過措置の利用の検討が必要となります。
選択届出書の提出期限は、基本的には適用しようとする課税期間開始の日の前日までと
なっているため、平成27年4月から簡易課税の適用を開始したければ、平成27年3月中に
検討し、提出有無を決定する、としてしまうと今回の経過措置の適用を受けることができま
せん。
経過措置の適用を受けたい場合には、平成26年9月末までに届出書を提出する必要があ
りますので提出漏れのないよう注意したいものです。
茨城本部 香川
2014,06,16, Monday
現オーナー経営者である父親も永年にわたる経営努力により会社の規模もそれなりとなり、
自身の年齢もそれなりとなると、次の後継者をだれにするか、そして自社株の相続税への
影響といった問題に直面します。
子供が後継者となることが決まっている場合は、相続時に想定される相続税の税率等を
比較しながら自社株の生前贈与を繰り返すことにより、いずれ訪れる相続税の負担を軽減
させることができます。
また、最近では贈与税の納税猶予の特例(特例を受けるためには、先代経営者は贈与時
までに自社の役員を退任する等の要件があります)を利用することによってより一層相続
税の負担軽減ができるようになりました。
ただ、ここで注意すべきこととして「遺留分」の問題があります。遺留分とは、民法において
遺族の生活の安定や最低限の相続人の間の平等を確保するために相続の権利を保障
するものです。
遺留分の額は遺産に一定の生前贈与財産を加え、負債を差し引いた財産である遺留分
算定基礎財産に法定相続分の2分の1(相続人が父母のみの場合は3分の1、兄弟姉妹は
遺留分なし)を掛けて算出されます。
そして、遺留分を侵害された遺留分権利者は、相続開始後に、受贈者・受遺者に対して
「遺留分減殺請求権」を行使することによって、贈与・遺贈財産の返還(又は価額弁償)を
受けることにより、遺留分を確保することができます。
となると例えば、相続人が子供のみ3人。相続財産は、現預金、不動産で5000万。
自社株は、現経営者である長男がすべて事業承継時に贈与を受けておりその当時の
相続税評価額が5000万。
このような場合、生前贈与された自社株は贈与時でなく、相続開始時の評価で計算される
ことから、相続開始時の評価額が現経営者の長男の努力の甲斐あって2億5000万円に
なったとすると、遺留分算定基礎財産は現預金、不動産と合算して3億円となります。
そうなると残り2人の兄弟は3億円の法定相続分3分の1のさらに2分の1にあたる5000
万円を遺留分減殺請求によって確保することが可能となり、長男は株式以外の相続財産で
足りない分については自身の保有する自社株を分散もしくは自身の所有する現預金を他の
兄弟に渡すこととなってしまいます。せっかく自身の経営努力によって会社の株の評価が
あがってもこの様な事態となってしまっては、本末転倒です。
この様な事態に対応するために経営承継円滑化法によって「遺留分に関する民法の特例」を
規定しております。
この民法特例を活用すると、後継者を含めた先代オーナー社長の推定相続人全員の合意
の上で、先代オーナー社長から後継者に贈与された自社株について、遺留分算定基礎財
産から除外(除外合意という)又は、遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の評価
額に固定(固定合意という)することができます。
除外合意をすると後継者が先代オーナー社長から贈与によって取得した自社株について
他の相続人は遺留分の主張ができなくなることから、相続によって自社株の分散を防止
することができます。
固定合意をすると自社株の評価が上昇しても遺留分の額に影響がないことから自身の
経営努力が想定外の遺留分を生みだすといった不条理なことは起こらなくなります。
この民法特例を利用するには、合意時点において3年以上継続して事業を行っている非上場
企業で先代オーナー社長が過去又は合意時点において会社の代表者であり、後継者は合意
時点において会社の代表者で自社株贈与により会社の議決権の過半数を保有しているという
要件を満たした上で推定相続人全員の合意を得て、合意した日から1カ月以内に「遺留分に
関する民法の特例に関する確認申請書」を経済産業大臣に申請し、経済産業大臣の確認を
受けてから1カ月以内に家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所の許可を受けることが必要です。
せっかく相続対策をしたつもりでも思わぬところでトラブルに巻き込まれることもあります。
自社株贈与については、万全の対策をとりたいものです。
埼玉本部 菅 琢嗣