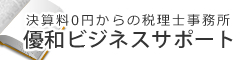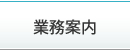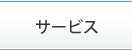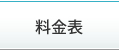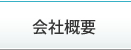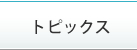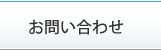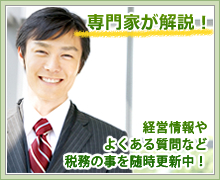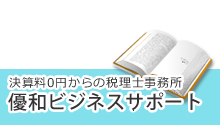国、地方公共団体や公共・公益法人等は、本来、市場経済の法則が成り立たない事業を
行っていることが多く、通常は租税、補助金、会費、寄付金等の対価性のない収入を
恒常的な財源としている実態があります。
このような対価性のない収入によって賄われる課税仕入れ等は、課税売上げのコストを構成しない、
いわば最終消費者的な性格を持つものと考えられます。
また、消費税法における仕入税額控除制度は、税の累積を排除するためのものですから、
対価性のない収入を原資とする課税仕入れ等に係る税額を課税売上げに係る消費税の額から
控除することは合理性がありません。
そこで、国、地方公共団体や公共・公益法人等については、通常の方法により計算される
仕入控除税額について調整を行い、補助金等の対価性のない収入(特定収入)により賄われる
課税仕入れ等に係る税額について、仕入税額控除の対象から除外することとされています。
特例計算の対象となる事業者は、次のとおりです。
① 国の特別会計
② 地方公共団体の特別会計
③ 消費税法別表第三に掲げる法人
④ 人格のない社団等
ただし、次に掲げる場合には、仕入控除税額の調整を行う必要はありません。
① その課税期間の仕入控除税額を簡易課税制度を適用して計算する場合
② その課税期間における特定収入割合が5%以下である場合
ここで、特定収入割合とは、その課税期間における資産の譲渡等の対価の額(税抜き)の合計額に
その課税期間の特定収入の額の合計額を加算した金額のうちにその特定収入の額の合計額を
占める割合をいいます。
仕入控除税額の調整を行う必要がある場合、原則的な方法により計算される課税仕入れ等の
税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の額を控除した後の金額を仕入控除税額とします。
このように、国、地方公共団体や公共・公益法人等については、その他の民間企業等と異なる
仕入控除税額の計算が必要となる場合があるため、注意する必要があります。
東京本部 小林
借地権の認定課税を受けない方法としては、次の方法があるか思います。
Ⅰ 相当の地代(固定方式・改定方式)
Ⅱ 無償返還方式
Ⅱの「無償返還方式」とは、文字通り「土地の使用後は、土地をタダで返す。」という
契約方法です。
何点か注意すべき点があり、列挙しますと、
①契約において、当事者の一方が法人であること
②期限までに税務署に届出書を提出すること
③契約書に「無償で返す」旨を記載すること
④地代を安くしすぎないこと 等
税務署は、土地の貸し借りついて権利金を支払わないでした場合、借主は貸主から
借地権を贈与されたものとみなします。(これが「借地権の認定課税」と呼ばれるものです。)
でも、「相当の地代」を払っているならば、権利設定による利益はないものとして、
課税しませんよ、としています。(法人税法)
しかし、「相当の地代」とは、簡単にいうと「土地の価格×6%」、100%÷6%=16.66・・
→16年強で、その土地そのものが買えてしまう高額な地代です。
社長が持っている土地を自分の会社に貸し、権利金や高額の地代を払うのはおかしい!
という意見が多くあり、昭和55年に「土地の無償返還に関する届出書」制度が制定されました。
将来、土地をタダで返しますと税務署に届け出れば、借地権の認定課税はしせんよ、という制度です。
順次、注意点を見ていきたいと思います。
① 契約において、当事者の一方が法人であること
無償返還制度は、法人税法で定められている為、契約当事者の一方又は両方が法人でないと
この届出書の提出はできません。
② 期限までに税務署に届出書を提出すること
一定の届出書に一定事項を記載して、賃貸借契約書・土地の評価明細等を添付して
税務署に提出します。
その際、”借地権の設定or使用貸借契約”を選択する部分がありますので、”借地権の設定”に
○をつけ、賃貸借契約により土地の貸し借りをしています!ということを示します。
これにより貸主に相続が生じた場合、8割評価や小規模宅地等の特例の使うことが可能となります。
ところで「期限」とは?
通達上は「遅滞なく」となっていますが、専門書の解説などには原則「賃貸借契約を結んだ法人の確定申告書の提出期限まで」となっていますので、その日までには提出。
③ 契約書に「無償で返す」旨を記載すること
賃貸借契約の一種ですから、契約書を作り、「無償で返す」旨を記載します。
無償返還方式は
「貸すとき権利金をとりませんので、返すときもタダで!」という契約ですので、契約書にもその旨を
きちんと書きます。
(例)
第○○条 (無償返還について)
土地賃貸借契約を解除する際は、借主は貸主に対し、何らの対価を求めず、本土地を無償にて
返還するものとする。
④ 地代を安くしすぎないこと
無償返還方式だと、地代は自由に決めることができます。(極論0円でもOK)
しかし、0円又は安すぎると相続が発生したとき、土地の評価が高くなってしまいます。
(使用貸借となって、自用地評価となります。)
ですから、一般的には
「固定資産税×2~3倍」といわれています。
(地代の認定という問題がありますが、ここではその説明は省略させていただきます。)
これらの注意点を踏まえ、無償返還方式を採用すれば、権利金や「相当の地代」のような
高額の地代を支払わず「借地権の認定課税」を避け、かつ、貸主に相続が発生した場合、
その土地については80%評価や小規模宅地等の特例(50%減or80%減)を適用することが
可能となります。
東京本部 根生