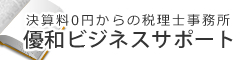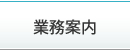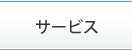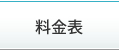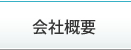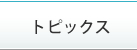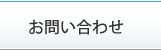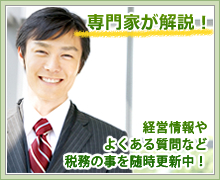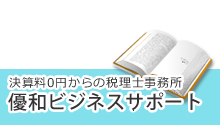2016,08,15, Monday
平成24年8月の「中小企業経営力強化支援法」の施行により創設された認定支援機関制度ですが、
今年で4年目を迎え、その制度も定着しつつあります。
認定支援機関が行う業務の中でも、特に次の3業務はその支援依頼が多いものとなっています。
① ものづくり補助金申請支援
② 中小企業経営力強化資金による資金調達支援
③ 経営力向上計画策定支援
① ものづくり補助金申請支援
まもなく2次公募の締め切りが迫っていますが、今年で3年目を迎えた設備投資による補助金で、
特に製造業を行う中小企業者にとってはメジャーな補助金となっております。
平成27年度の1次公募では、iot分野として最大3千万円まで補助金の上限が増加しており、
また、その適用対象者にサービス業も追加されたことから、多くの中小事業者が興味を持たれている
補助金です。
② 中小企業経営力強化資金による資金調達支援
日本政策金融公庫から受ける融資制度で、認定支援機関による事業計画書の作成支援から
モニタリングを受けることで、低金利での資金調達が可能となります。
これまでの日本政策金融公庫による創業融資制度より低金利で、かつ、自己資金要件がないという
低いハードル設定で、創業や新たな事業展開を検討される方を支援する制度です。
③ 経営力向上計画策定支援
固定資産税(償却資産税)の3年間半減という、はじめての特例措置に多額の設備投資を行う
事業者にとってはとても魅力的な国の制度です。
平成27年度ものづくり補助金2次公募でも加点対象とするくらい、国からのイチオシの制度です。
税理士法人優和ではこれら認定支援機関業務に他の事務所より先駆けて取り組みを実施しており、
数多くの実績をあげております。
認定支援機関をお探しの方は、ぜひ、当社までご一報下さい。
京都本部 太田
2016,05,16, Monday
公益法人は、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するために活動することが
求められることから、その事業運営において透明性が確保されている必要があります。
このため、公益法人は、(1)事業計画等、(2)事業報告等に関する書類の作成、
提出及び開示が求められています。
(1)事業計画等
公益法人は、毎事業年度開始の前日までに、当該事業年度の事業計画書、収支
予算書及び資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(事業計画等)を作成し、
当該事業年度の末日までの間、事業計画書等を主たる事務所に、その写しを従たる
事務所に備え置く必要があります(認定法第21条1項、認定法施行規則27条)。また、
これらの書類について、毎事業年度開始の前日までに行政庁に提出する必要があり
ます(認定法第22条1項)。
(2)事業報告等
公益法人は、法人法で定める計算書類等(貸借対照表及び損益計算書、事業報告
並びにこれらの附属明細書(監査報告書又は会計監査報告を含む。)のほか、毎事業
年度経過後三箇月以内に、財産目録、役員等名簿、役員等の報酬等の支給の基準を
記載した書類、キャッシュ・フロー計算書(作成している場合)、運営組織及び事業活動
の状況の概況及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類を作成し、これ
らの書類を五年間主たる事務所に、これらの書類の写しを三年間従たる事務所に備え
置く必要があります(認定法第21条2項、認定法施行規則第28条1項)。また、これらの
書類について、毎事業年度経過後三箇月以内に行政庁に提出する必要があります
(認定法第22条1項)。
東京本部 小林
2016,03,15, Tuesday
『遺留分に関する民法の特例』とは、一定の要件を満たす中小企業の後継者が
遺留分権利者と合意し、所要の手続きを経た場合に遺留分算定で特別な計算が
できる制度です。
後継者が安定的に経営をしていくためには、生前贈与などににより自社株式や
事業用資産を集中的に継承させることが必要となります。
しかし、被相続人の事業を引き継ぐ後継者以外の相続人からの遺留分減殺請求
により、後継者が事業継続に必要な自社株式等を放出せざるを得なくなるときもあります。
このような問題に対処するため、経営承継円滑化法では遺留分に関する民法の特例
(遺留分特例制度)が規定されています。
■遺留分算定に係る特例
遺留分算定に係る特例とは以下のようなものです。
(1)除外合意
先代の経営者から後継者へ生前贈与した自社株式等について、遺留分算定の基礎
財産から除外することができます。
これにより、自社株式等に係る遺留分減殺請求を未然に防止することができるようになります。
(2)固定合意
遺留分算定基礎財産に算入する価格を合意時の時価に固定することができます。
これまでは、贈与後会社の業績を伸ばし会社の株式価値が増加した場合には、
株式価値を増加させた分まで遺留分算定の対象になってしまいましたが、固定合意により
後継者が株式価値上昇分を保持でき、経営意欲の阻害要因を排除することができます。
この特例を利用するには、いずれも推定相続人全員の合意により、書面で定めをする
必要があります。
また、その上で経済産業大臣の確認、及び家庭裁判所の許可を受けることが必要となります。
手続きの煩雑さからこの特例の利用は敬遠されがちではありますが、28年4月から
後継者が親族外のものでも対象となるよう拡充されましたので事業継承の解決策の
一つとして上手に利用していきたいものです。
茨城本部 香川
2016,02,15, Monday
平成28年度税制改正によると、太陽光発電設備等の取得による特別償却又は税額控除を適用できるいわゆるグリーン減税が平成28年3月31日をもって現行法としては終了することとなります。現行法は、発電した電力を売電する太陽光発電設備について国の認定を受けた設備について、減税を受けることができましたが、平成28年4月1日以降の新法は国の認定外の自家用として電力を使用するものに限った太陽光発電設備について平成30年3月31日までの2年間に限り減税の適用が受けられます。
したがって、現行法の認定発電設備については、今年の3月31日までに取得しなければ、適用を受けることができません。これはあくまで取得日で判断するため、かなり気を付けたいところです。
話は変わりますが太陽光発電設備に関連して、給与所得者であるサラリーマンのお宅の屋根に取り付けられている太陽光発電設備における売電収入についても確定申告が必要になる可能性があります。
どのようなケースで確定申告が必要となるかというと給料以外の年間所得が20万円を超える場合に必要となります。
年間20万円の売電収入?と思われるかも知れませんが、所得とは収入から経費を差し引いたものを言いますので、太陽光発電の場合だと収入は売電収入、経費は太陽光発電設備の減価償却費ということになります。
例えば340万円の太陽光発電設備を購入して年間売電収入が40万円だとします、そのうち年間発電量が8,000kwで年間売電量が6,000kwとした場合、収入金額40万円から減価償却費340万円÷17年(太陽光発電設備の耐用年数が17年)×6,000÷8,000(年間発電量のうち売電量に対応する分のみを経費算入します)=15万円を差引いたところ25万円となるため、この場合確定申告が必要となります。
注意すべき点は太陽光発電設備の減価償却が全額経費算入できず年間発電量のうち売電部分に対応する分のみというところです。
税金は、これだけではありません。市区町村で課税される償却資産税です。個人のお宅で発電出力10kw以上の設備の場合、課税対象となり課税標準額に対し1.4%の償却資産税が課税されます。ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けた設備である場合、課税初年度から3年分については課税標準額が3分の2となります。
うっかりすると見落としがちですが、今年の確定申告ではこのような相談も多くなりそうです。
埼玉本部 菅 琢嗣
2016,01,15, Friday
公益法人が公益目的事業のために取得、形成した財産が、法人内部で死蔵されることなく、
速やかに公益目的事業に使用されるよう、事業に現に使用されておらず、使用の見込みもない
財産の額について、保有可能な上限額を設けられています。
遊休財産額とは、公益目的事業又は収益事業その他の業務若しくは活動のために現に
使用されておらず、かつ、引き続きこれらのために使用されることが見込まれない財産の
合計額のことをいいます。遊休財産額の保有の制限とは、公益法人の各事業年度の末日に
おける遊休財産額がその年度の公益実施費用額(公益目的事業の実施に係る費用の額)を
超えてはならないという制限です。
遊休財産額が上限額を超えない見込みであることが認定基準であり、認定後において、
この基準を満たさなくなった場合には、公益認定が取り消されることがあります。
東京本部 小林
2015,10,01, Thursday
以前から富裕層に対しては、確定申告で所得が2000万円以上の納税者に対し
財産債務明細書の提出を義務付けたりして資産状況の管理を行っていましたが、
このところ国税当局は富裕層への課税強化に本気で乗り出してきたようです。
特に重点的に管理すべき「超富裕層」とその関連法人については、「重点管理富裕層」
として、その海外取引や相続対策等による資産の移動等についても中長期的に管理・
把握をしてくということだそうです。
重点管理富裕層に指定されると、それらは「課税上の問題が想定され調査企画の着手が
相当と認められる者」「課税上の問題は顕在化しないが多額の保有資産の移動が見受け
られるなど継続的な注視が必要と認められる者」「課税上の問題等は現在見られないが
経過観察が妥当と認められる者」と3つのカテゴリーに区分され、すべての富裕層がすぐに
調査ということにはならないものの、調査対象となった場合、通常の税務調査よりもさらに
踏み込んだ調査が行われるようです。
では、この「超富裕層」とよばれる大口資産家は、どのように選定されるのでしょうか?
国税庁は、その選定基準については正確な事実の把握を困難にする恐れがあることから
非公開としていますが、9月3日付の日本経済新聞によると、複数の国税OBらに取材した
結果、次の10個の選定基準が判明したとのことでした。
①有価証券の年間配当4000万円以上
②所有株式800万株以上
③貸金の貸付元本1億円以上
④貸家などの不動産所得1億円以上
⑤所得合計額が1億円以上
⑥譲渡所得及び山林所得の収入金額10億円以上
⑦取得資産4億円以上
⑧相続の取得資産5億円以上
⑨非上場株式の譲渡収入10億円以上、または上場株式の譲渡所得1億円以上かつ45歳以上のもの
⑩継続的または大口の海外取引があるもの、または①~⑨の該当者で海外取引があるもの
これだけを見ると通常の確定申告等ではあまりお目にかかる数字ではなく、ピンと来ませんが、
あくまで超富裕層の多い東京を前提としたものであるらしく、地方に行けばそのラインも
必然的に下がってくるとのことで、そうなるとすべてが他人事でもなくなってくるのではない
でしょうか。
上記に該当する大口資産家については税務署ごとに調査ファイルが作成されており、
資産状況や資金の流れが厳密に管理されているとのことです。
今後は、事業承継、自社株対策等を行うにあたっても、今まで以上に常に「国税の影」を意識
せざるを得ないこととなりそうです。
埼玉本部 菅 琢嗣
2015,08,15, Saturday
最近はテレビCMでも良く耳にするようになった「クラウド会計」ですが、皆様の会社では
どのような会計ソフトを使用されていますか。
税理士法人優和では早くから「優和の楽ラクWeb会計」というクラウド会計を開発し、
お客様に提案しております。
このシステムは実は会計ソフトで圧倒的なシェアを誇る「弥生会計」をベースに構築された
ものなので、使いやすいと好評です。
今回は、このクラウド会計を導入したお客様から頂いた意見をまとめてみました。
①低コスト
初期費用不要で毎月使用料を支払って使用する、いわばレンタルといった感じでしょうか。
当然にバージョンアップ費用も無料。しかも自動更新。
⇒購入型の会計ソフトも購入費以外に毎年の保守料やバーションアップ料が必要であるため、
コスト削減には明らかにメリットが感じられます。
②サーバー不要
ネットバンキングシステム並みのセキュリティが整備されているため、社内サーバーで保管
するより断然安全。
⇒会計データを社内で保管する必要がないため、サーバーコストも削減可能。
③会計データのリアルタイム共有
税理士とのリアルタイムな情報の共有が可能
⇒収支状況の把握だけでなく、その使用方法についてもネット環境さえあれば分かりやすく、
かつ、すぐに教えてもらえる。
主にこの3つが寄せられる意見で多いようです。
特に、③のお客様と税理士が別々の環境にいながら同じ画面上で話ができる点に魅力を
感じて頂けている方が多いようです。
また、最近ではマインバー対策として、セキュリティ強化面で社内サーバーからクラウド化へ
の移行が進んでおり、クラウド会計の普及が進んでいます。
ちなみにこの「優和の楽ラクWeb会計」ですが、弥生会計その他の会計データの取り込みが
できますので、乗り換えもラクラクです!
ご興味のある方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談下さい。
京都本部 太田芳樹
2015,08,01, Saturday
5月27日に『空き家対策特別措置法』が施行されました。
この措置法を簡単に説明すると、①安全面で危険なもの②衛生上有害になる恐れがあるもの
③著しく景観を損なっているもの、そのような空き家に対して市区町村が所有者に修繕や撤去
を命令することができます。
もし、所有者がその指示に従わなかった場合は、最終市区町村のほうで撤去することができる
というものです。
全国には820万戸の空き家があると言われており、年々増加傾向にあります。
人口の減少が続けば大きな社会問題になるため、それを防止するためにできた措置法です。
この法律ができたことにより、中古市場に今までなかった物件が出回り、住宅市場の活性化に
繋がると思います。
また、空き家を有効利用するといっても思い浮かぶのは、賃貸がありますが、実際にそれを行う
には課題があったり、費用もかかったりで、分かっていても決断ができないのが現状ではないで
しょうか?
住んでいない、全く手入れをしていない、見に行くこともしていない物件をお持ちの方は要注意
です。今はまだ問題ありませんが、10年後、20年後にはこの措置法の対象になってしまうことが
あります。
ぜひ有効活用できるうちに当事務所へご相談下さい。
京都本部 中村
2015,07,15, Wednesday
平成28年よりマイナンバー制度の利用が始まります。
今回は、マイナンバー制度のうち個人番号について触れたいと思います。
マイナンバーとは日本に住民票を有する全ての人に割り振られる12桁の番号で、
原則として一生変更されることはありません。
このマイナンバー制度の導入に伴い、平成27年10月以降、住民票のある住所宛に
各市区町村からマイナンバー(個人番号)の通知カードが、各世帯ごとに1通ずつ
書留にて送付されます。
受取を拒否すればマイナンバー制度そのものを拒否できるのでは、などという飛語
が出回っているようなことも耳にしますが、通知カードの受領有無に関わらず、日本
に住民票を有する全ての人に番号は割り振られていますので、仮に通知カードの
受取を拒否してもマイナンバー制度を拒絶することはできません。
むしろ、自分のマイナンバーが解らないと、今後マイナンバー制度の導入によって
開始される各種サービスや情報の提供などを受けられなくなる場合もありますので、
住民票の住所と実際に住んでいる住所が違う方は早めに住所変更をされることを
お勧めいたします。
また、マイナンバーは10月より送付が始まる通知カードの他、希望される方につい
ては個人番号カードの交付を受けることができます。
個人番号カードは住民基本台帳カードと同様、ICチップの搭載が予定されており、
表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー
(個人番号)を記載する予定です。
本人確認のための身分証明書として使用でき、図書館カードや印鑑登録証など
自治体等が条例で定めるサービスやe-Tax等の電子申請等が行える電子証明書
も標準搭載されます。
一方、通知カードの場合、そこに記載される情報は個人番号と個人識別情報だけ
で顔写真の掲載がないため、本人であることの証明をすることはできません。
併せて本人であることを証明する書類の提示(運転免許証や写真付き住民基本
台帳カードなど)が必要となります。
写真付き個人番号カードの交付を受ければ、一枚でマイナンバーの提示と本人
であることの証明が可能ですので、平成28年1月以降に各市区町村で受付が
始まったら速やかに交付手続きを行うことが推奨されています。
このマイナンバーですが、実際平成28年度からどのような場面で利用されるかというと、
所得税:平成28年分の申告書から
法人税:平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から
法定調書:平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから
申請書等:平成28年1月以降に提出すべきもの
等があります。
雇用している個人事業主・法人のマイナンバーだけでなく、雇用されている従業員の
マイナンバーを記載すべき書類もあります。
企業や事業主が従業員等の雇用している人々のマイナンバーを必要書類に記載す
るために取得する場合には本人確認が必須となっています。
従業員のマイナンバーを取得する際、企業は、利用目的の明示と厳格な本人確認が
必要です。
この場合の本人確認では、正しい番号であることの確認(番号確認)と番号の正しい
持ち主であることの確認(身元確認)を行わなければなりません。
個人番号カードを持っている場合は、そのカードのみで本人確認が可能ですが、
持っていない場合は、通知カード(住民票の写し)と運転免許証やパスポートで行います。
例えば年末調整などの場合、従業員のマイナンバーは勿論、その従業員に扶養家族が
いる場合その家族のマイナンバーも取得する必要があります。
この場合、従業員の家族のマイナンバーについて本人確認を行い、企業側に通知をする
のは従業員本人となりますが、一方、国民年金の第3号被保険者の届出では、企業が従
業員の配偶者(第3号被保険者)の本人確認を行うこととなります。
このように、平成28年度からは従業員やその家族のマイナンバーも取り扱う必要が出て
くるため、安全管理体制の整備は必須となります。そもそも、情報漏洩は信用問題にも
なりますし、情報を悪用されるおそれもありますので、その管理には十分に注意する必要が
あります。
マイナンバーの運用開始まで半年を切り、通知開始までは残すところ2か月余りです。
私たち個人としても、企業としても他人事ではない制度のスタートとなりますので、しっかりと
準備したいものです。
茨城本部 香川
2015,07,01, Wednesday
持株会社のメリット・デメリットについて、簡単に記載したいと思います。
持株会社とは、具体的な事業活動を行わずに他の会社を管理・指導する会社です。
最近では、上場企業の多くで〇〇ホールディングスといった社名が聞かれます。
では、なにゆえ持株会社(ホールディングカンパニー)を設立するのでしょうか?
上場企業で持株会社が広く活用されていることには以下の点があると考えられます。
1.持株会社の下に各事業会社を紐付けるため、各事業会社の業績把握が容易である。
2.事業会社の下に事業会社を紐付ける場合には、親子会社間の軋轢や摩擦が生じやすい。
その点、持株会社は事業会社ではないので、こうした軋轢等の心配が少ない。
3.損害賠償請求やその他の企業リスクを分散・遮断することができる。
上記のようなメリットを考えると中小・零細企業にとっては持株会社を設立する意義が
あまりないようにも思われます。
しかし、以下の理由から中小企業でも持株会社を設立するメリットは大いにあります。
理由は以下のとおりです。
1.相続税の節税メリット(資産の含み益に対する法人税等相当額38%控除)
①オーナー ⇒ A社の場合
A社の利益及び純資産額(時価)を基準にA社株式が評価される。
②オーナー ⇒ H社 ⇒ A社の場合
H社の利益及び純資産額(時価)を基準にH社株式が評価される。
H社が保有するA社株式について含み益がある場合は、上記の法人税等相当額38%を
控除することが出来る。
H社(持株会社)を設立した当初は、A社(事業会社)とH社の株式評価は同一となり
節税効果はありません。
設立後、長期間にわたってA社が高い収益をあげることによるA社株式の含み益に
対して38%が控除され、節税になります。
上記法人税等相当額38%の控除についてですが、「法人の含み益が顕在化するのは
売却した時であり、売却した時には実効税率分の税負担がある。ゆえに税負担分は
控除する」という内容です。
2.事業承継対策としてのメリット
複数法人を所有している場合に、会社ごとに株式を後継者へ移転していくことになります。
一方、持株会社を設立すれば、当該持株会社株式を移転させるのみで足ります。
但し、承継させたい親族が複数いる場合には持株会社化していることがかえって
煩わしくなってしまうこともありますので、ご注意ください。
ちなみに、持株会社を設立するためには以下の手法が考えられます。
①株式交換による方法(既存法人を持株会社にする方法)
既存法人株式の全部を他の株式会社に取得させる手法
②株式移転による方法(新設法人を持株会社にする方法)
既存法人株式の全部を新設法人に取得させる手法
なお、上記の株式交換や株式移転を行う場合には、税制適格要件があり、
当該要件を満たす場合には簿価引き継ぎ、満たさない場合には時価引き継ぎ
(税制非適格)となります。
税制非適格とみなされる場合には、含み損益に対する課税が発生するため
注意が必要です(ただし、100%グループ内組織再編であればグループ法人税制により
課税が繰り延べられます)。
茨城本部 楢原英治