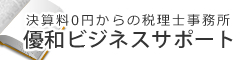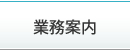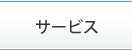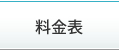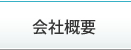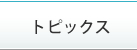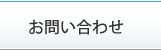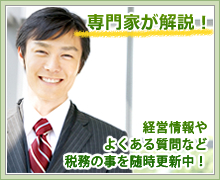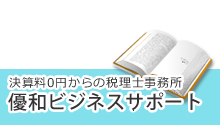2015,05,15, Friday
「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が
平成26年6月20日に可決成立し、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」
(以下、一般法人法という。)が改正され、平成27年5月1日より施行されました。
一般法人法が適用される一般社団法人等においては注意が必要となります。
改正の主な内容は、以下の三点です。
① 外部役員等の概念の廃止及び非業務執行理事等の概念の導入
② 責任の一部免除の拡大及び責任限定契約対象者の拡大
③ 監事の会計監査人の選定・解任等の権限の拡大
①外部役員等の概念が廃止され、非業務執行理事等の概念が導入されました。
従来は外部理事(現在及び過去において、当該一般社団法人又はその子法人の
業務執行理事又は使用人となったことがない理事)、外部監事(過去に当該一般社
団法人又はその子法人の理事又は使用人となったことがない監事)、又は会計監査
人を外部役員等としていましたが、改正法においてその概念が廃止され、新たに非
業務執行理事等の概念が導入されました。
ここで、非業務執行理事等とは、理事(業務執行理事又は当該一般社団法人の使
用人でないものに限る。)、監事又は会計監査人をいいます。
非業務執行理事等は、従来の外部役員等を包含する広い概念となっています。
②上記①の非業務執行理事等の概念の導入に伴い、従前の外部理事以外の理事
であって業務執行を行っていない者については、責任の一部免除(一般法人法113条
1項)が拡大(最低責任限度額が減少)しています。
また、非業務執行理事等であれば、責任限定契約の対象となることとなり(一般法人
法115条)、従前の外部理事等の概念と比べると、責任免除の対象者が広がりました。
③会計監査人の選定・解任等については、従来は理事が議案を社員総会に提出する
場合等において、監事の同意を必要としていましたが、改正法では選定・解任等の議
案の内容の決定権限そのものが監事のものとなりました(一般法人法73条)。
今回の改正に伴い、一般法人法115条に基づき定款において責任限定契約に関する
規定を設けている法人において、定款変更が必要となるのかが実務上の問題と
なっています。
この点、今後も従来の外部役員等に限定して責任限定契約を締結するという法人に
おいては、定款変更の必要はないと考えられています。
すなわち、改正法では従来の外部役員等を含む広い概念である非業務執行理事等
との間で責任限定契約を締結することができますが、今後も従来の外部役員等の
概念に当てはまる者としか責任限定契約を結ばないという場合には定款変更の必要は
ないと考えられています。
逆に、責任限定契約を締結する対象を非業務執行理事等に広げたい場合には定款変更
が必要であると考えられています。
今回の改正による定款変更の要否は法人ごとに異なるため、各法人において検討する
必要があります。
東京本部 小林 歩
2015,04,15, Wednesday
中小企業者と中小法人の違いは何?
簡単そうですが、意外と税理士事務所の人間でさえしっかりと回答できる者は
少ないでしょう。 どちらも資本金が1億円以下の法人という点では同じです。
では違いは何なのでしょうか?
中小企業者は、次のいずれにも該当しない法人をいいます。
①発行済株式の1/2以上が同一の大規模法人(資本金が1億円超)に所有されている。
②発行済株式の2/3以上が複数の大規模法人に所有されている。
中小企業者に該当すれば、30万円未満の固定資産を損金算入できる特例、
中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却(一定の場合には特別控除)などの
適用を受けることが出来ます。
一方、中小法人は資本金5億円以上の大法人に100%所有されていない法人をいいます。
中小法人に該当すれば、法人税率の軽減税率、交際費の損金不算入における定額控除
限度額、貸倒引当金繰入の損金算入、青色欠損金の全額損金算入などの適用があります。
以上のように、とても大切な規定が適用できるか出来ないかを判定する上で
大変重要なものとなります。
今一度、株主の資本金も調べた上で適用の有無を確認しましょう。
詳細は税理士法人優和の各担当者までお問い合わせ下さい。
京都本部 中村 真紀
2015,04,01, Wednesday
会社の決算書類はいわば成績表のようなものです。
先日、新規のお客様が来られ決算書をみていると、多額の営業損失となっていました。
業績のよい会社と思っていたのになぜ?
ヒアリングをすると、昨年先代が亡くなられ役員退職金を支給したとのこと。
さらに調べていくと社葬費用も雑費に計上されていました。
30年以上も代表取締役をされた社長様に対する役員退職金や社葬費用を
単純に販売費及び一般管理費で表示してしまうと、営業損失になってしまい
非常に見栄えの悪い決算書になってしまいます。
外部の利害関係者(金融機関等)に対してもいちいち説明をしないといけません。
簡単に処理するだけではなく、お客様に喜ばれる決算書を作成してこそ
商品価値が高まります。
税理士法人優和は、これからもお客様に喜ばれる決算書作成をしていきます。
京都本部 中村 真紀
2015,02,01, Sunday
平成27年より、相続税の基礎控除及び税率について一部改正があり、
巷では「相続大増税時代」などということをよく聞くようになりました。
特に基礎控除の引き下げについては、その影響が強く、我々顧問先のオーナー社長に
とっては最大の関心事といっても過言ではなく、この頃「相続税の試算をして欲しい」と
いう依頼を受けることが以前と比べて多くなったように感じられます。
その中でも、自社の株式の評価額が「これ(自社株)さえなければ相続税もそれほど
かからないのに」といったケースも多く見受けられます。
そこでオーナー社長が保有している自社の株式を生前に相続人たる後継者に贈与
もしくは譲渡するといったいわゆる事業承継(具体的には株式の承継)が行われます。
一般的に考えられる株式の承継対策としては、次のような方法が考えられます。
(1)株式を贈与し、暦年課税方式により贈与税の申告をする。
(2)株式を贈与し、相続時精算課税方式により贈与税の申告をする。
(3)株式を贈与し、贈与税(相続税)の納税猶予制度の適用を受ける。
(4)後継者が出資する資産管理会社(もしくは後継者個人)に株式を譲渡する。
(1)の方法については、最もポピュラーで古典的な方法かも知れませんが、
長い年月をかけ、贈与税の基礎控除110万円前後の範囲内で毎年贈与を繰り返すことで
効果を発揮しますが、以前(26年6月15日号)もブログに書いた様に遺留分の減殺請求等
に十分注意する必要があります。
また、株主たるオーナー社長がそれなりに高齢の場合、思ったほどの効果はなく、
その時は、相続税の税率と比較しながらある程度の贈与税の税負担を覚悟で
大胆に贈与していく必要もあります。
(2)の方法については、贈与時には株価が2500万円までは贈与税がかからず、
それ以上の場合は、2500万円を差し引いた金額に20%の贈与税がかかり、
その後相続発生時に贈与時の株価で相続税を改めて精算する方式です。
未来を予測することは困難ですが、贈与後会社の業績が著しく上昇した場合は、
結果的に相続時精算課税制度を選択して良かったということになりますし、
逆の場合も当然考えられます。
(3)の方法については、一定の要件を満たせば、発行済み株式の3分の2を限度
として贈与税の納税が猶予(その時点では、納税額ゼロということになります)
されるというものですが、申告後5年以内に一定の要件を満たさないこととなった場合、
当初払うべき贈与税の他延滞税等もかかってしまいます。
M&Aで会社を売却したり、不況で従業員をリストラする場合は、この納税猶予の
一定の要件のシバリの為にそれらを断念するという事態も考えられます。
(4)の方法については、上記3つの方法とは毛色が全く異なる方法で、後継者たる
相続人が資産管理会社を設立し、金融機関からの借入でオーナー社長所有の自社
株式を買い取り、オーナー社長は株式譲渡所得の20%の所得税住民税を支払い、
オーナー社長に利益が還元され後継者への株式の承継も完了しますが、
上記3つと異なり譲渡所得で得た利益は、何もしなければ当然相続財産となり、
多額の相続税を支払うことにもなりかねません。
したがって、株式譲渡により事業承継は完了したかもしれませんが、生前相続対策
としては「道半ば」ということになります。
金融機関は、この方法が大好きで融資金額も多額となりますし、会社に事業承継
対策として勧めてくる場合、十中八九このスキームのような気がします。
生前の株式承継対策としては以上のような方法が主に考えられますが、
必ずしもどの方法が良くてどの方法はダメだということはなく、どの方法にも
一長一短があり、要は会社の内情によって最も適した方法をチョイスしていくことが
大切なのではないでしょうか。
(場合によっては、納税額が多くなる方法を選択するケースだってあるかと思います)
今のうちに煩わしい「事業承継対策」について、ある程度のしっかりとした道筋をたてて、
後は本業に専念したいものです。
埼玉本部 菅 琢嗣
2014,10,01, Wednesday
共通番号法、いわゆる「マイナンバー制度」が、平成27年10月より導入される予定です。
具体的にこの、マイナンバー制度とはどのようなものかというと、我々全国民及び全法人等に
固有の番号(個人が12桁で法人が13桁)が割り当てられ、その番号を用いて収集した情報を、
社会保障・税などのために複数の府省庁や地方公共団体の間で利用される、いわゆる
「情報連携」が行われます。
そして、この番号を利用した成りすましを防止するために、これまで利用されてきた住民基本
台帳カードを改良した「個人番号カード」が全国民一人ひとりに当該個人の請求に応じて交付
するときに本人確認の仕組みが作られます。
それでは、この「マイナンバー制度」によって税金関係はどのように変わっていくのかというと、
確定申告においても自分の登録情報などをインターネット経由で確認することができる
「マイ・ポータブル」によって、給与や報酬の情報、年金保険料、国民健康保険料等の社会保険
料支払情報、株式配当、譲渡損益、保険満期返戻金、保険年金等の金融所得情報、過去の
税務申告・納付情報といったものが日本年金機構、各自治体、金融機関、企業、税務当局が
一体となって把握することが可能となります。
ここまでの話だと、とても効率的で素晴らしい制度のように思えますが、実際導入する段階に
おいては様々な問題点や疑問点も浮き彫りとなってきます。
例えば、平成27年10月に市区町村を通じて割り当てられた個人番号を金融業界などは、
株式配当金や保険金の支払いなど国税庁に提出する法定調書に個人番号を記載するために、
証券口座や保険契約などについて顧客に個人番号の申告を受ける義務が生じます。
また、一般企業においても従業員の給与支払いを国税庁や地方自治体に報告したり、
企業や健康保険料の支払・給付を管理するために、従業員に個人番号を申告してもらう必要が
生じます。
実際には、平成27年中にこれらの一連の業務を行うことはかなり負担になるのではないかと
思われます。
税務申告については、平成28年分から適用となるようですが、平成27年10月は、
順調にいけば、消費税増税に時期と重なりますし、今後の対応について十分注意する必要が
ありそうです。
埼玉本部 菅 琢嗣
2014,09,17, Wednesday
先般記載させていただいております、「NPO法人会計」につき2012年4月1日施行「新会計基準」の
大枠(その3・最終回)を記述いたします。
⑨ その他の事業で得た利益を特定非営利活動に係る事業に繰り入れる場合の表示
活動計算書の「当期正味財産増減額」の上に「経理区分振替額」という勘定を設け、
その他の事業の区分において繰入額分をマイナス計上するとともに、同額を特定
非営利活動に係る事業の区分においてプラス計上することとなる。
⑩ 収支計算書から活動計算書への移行
新会計基準適用初年度の活動計算書の「前期繰越正味財産額」に、適用直前期末の
貸借対照表の「正味財産合計」の金額を記載することが必要となる。
⑪ 期首の貸借対照表・財産目録の引継ぎ
新会計基準適用初年度の貸借対照表・財産目録は、前期末に作成された貸借対照表
をそのまま引き継ぐことになる。
⑫ 「会計の明確に関する研究会報告書」が示す、現状の会計から移行するに当たっての
経過措置
A)過年度分の減価償却費
従来、減価償却を行っていなかった場合には原則として適用初年度に過年度減価償却費を
計上することになる。
ただし、期首の簿価を取得価額とみなし、当該年度から、減価償却することも容認されている。
この場合の耐用年数は、新規取得時の耐用年数から経過年数を控除した年数とし、その旨を
重要な会計方針として注記することとなる。
なお、従来資産計上せず購入時費用処理したものについては、過年度損益修正益を計上し、
資産計上する必要はない。
B)退職給付会計導入に伴う会計基準変更時差異
退職給付会計を導入しようとする場合の、会計基準変更時差異については、適用初年度から
15年以内の一定の年数にわたり定額法により費用処理することになる。
この処理は、会計基準変更時に一括して経常外費用の過年度損益修正額として計上することも
含まれる。
また、既に退職給付会計の導入が行われている場合は、従前の費用処理方法を継続する。
C)過年度分の収支計算書の修正
収支計算書から活動計算書へ変更したとしても、それは制度改正に基づくものであるから、
継続性の原則に反するものではなく、表示方法の変更等について遡って修正を行う必要はない。
D)正味財産の区分
正味財産を区分して記載する場合も、遡及修正を行う必要はない。
E)適用初年度における「前期繰越正味財産額」
上記⑩参照
F)収支予算書及び収支計算書による代替
NPO法附則(平成23年6月22日法律第70号)により当分の間、活動予算書、活動計算書に
代えて収支予算書、収支計算書を作成することが認められている。
東京本部 笠田朋宏
2014,09,01, Monday
平成24年にマイナンバー法案(社会保障・税番号制度)が成立しました。
今まで、年金番号、健康保険の記号、確定申告時の整理番号等、目的により
番号がすべて違いましたので、縦割行政の弊害を取り除いて、国民の利便性の
向上を図れることがメリットです。
平成27年後半には、個人番号カードが市町村より送付されてくる予定です。
マイナンバーにより、確定申告に添付する国民年金の控除照明書が不要と
なってきます。
マイナンバー制のように国民にID番号を付す制度は、各国行っています。
お隣の国、韓国をはじめとして、デンマーク、アメリカ、フランス、ドイツなど
ID制度を採用しています。
ただし、その成立の経緯が異なるためその利用範囲に関しては、
各国異なるようです。
デンマークは、福祉が充実しており税金福祉からIDにより納税医療から教育の
分野まで広く利用されているようです。
ドイツなどは、個人情報の保護等の観点から税金に関するもののみに
利用されています。
日本では、社会保障と税に限定されて始まりましたが、早くも預貯金等にも
マイナンバーを適用するとの政府の決定がなされました。
利便性が向上するのは良いのですが、くれぐれも情報の漏えいにだけは
注意を払ってほしいものです。
税理士法人優和 東京本部 市川
2014,05,15, Thursday
先般記載させていただいております、「NPO法人会計」につき2012年4月1日施行「新会計基準」の
大枠(その2)を記述いたします。
(5)会費の取扱い
確実に入金されることが明らかな場合を除き、実際に入金したときに収益として計上する。
たとえ、当期に入金があったとしても、翌期以降に帰属するものは前受けに
振り替えるものとする。
また、未収計上も回収可能性が確実にあると認められる場合にのみ計上が認められる。
なお、サービスの対価としての性質がある会費は、サービス提供時点で、収益を計上すること
となる。
(6)特定資産の計上
寄付者の意思や法人の意思に基づいて、特定の目的のための資産を保有する場合には、
当該目的を示す独立科目によって、独立表示することとなっている。なお、公益法人会計基準と
異なり、必ずしも固定資産でなくてもよく、流動資産でもよい。
(7)無償等で財・サービス・役務提供を受けた場合の取り扱い
無償または、著しく低い価格で施設の提供等を受けた場合には、事業報告書に記載するのみ
ならず、財務諸表に示すことも認められている。その場合には2つ方法があり、一つは金額を
合理的に算定できる場合に財務諸表に注記する方法であり、もう一つの方法は金額を客観的に
把握できる場合に注記に加えて、活動計算書に計上することもできる。
また、ボランティアによる役務の提供を受けた場合には、活動の原価の算定に必要な受入額分を、
上記と同様に処理することが認められている。なお、会計処理としては、受入評価益として収益
計上するとともに同額を、評価費用として費用処理することとなる。
(8)その他の事業で得た利益を特定非営利活動に係る事業に繰り入れる場合の表示
活動計算書の「当期正味財産増減額」の上に「経理区分振替額」という勘定を設け、その他の
事業の区分において繰入額分をマイナス計上するとともに、同額を特定非営利活動に係る事業の
区分においてプラス計上することとなる。
東京本部 笠田朋宏
2014,01,14, Tuesday
今回もNPO法人の会計について記載いたします。
旧来NPO法人の計算書類は、正確性・法人比較可能性に劣り、不備があるなど欠点がありました。
そこで以下、共通集約的目安としての2012年4月1日施行「新会計基準」の大枠を記述いたします。
(1)区分経理が必要
NPO法第5条においては、「その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う
特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければなら
ない」とあることから、特定非営利活動に係る事業とその他の事業の区分経理が求められている。
ただし、実務的に貸借対照表を区分経理することは困難と考えられることから、貸借対照表は
区分経理せず、活動計算書のみを区分経理することも認められている。
なお、法人税法施行令6条においては、法人税法上の収益事業と非収益事業との区分経理が
求められている。この点、NPO法上の特定非営利活動に係る事業と法人税法上の非収益事業が
必ずしも一致するものではなく、また、NPO法上のその他の事業と法人税法上の収益事業が必ず
しも一致するものではない。ゆえに、決算時に法人税法上の区分に再集計して、税務上の活動計
算書を作成することが必要となる。
(2)事業費・管理費の区分、活動計算書の内訳表示、共通経費の按分
会計基準14においては、事業費と管理費に区分して表示することを規定している。そして、
注解1-4においては形態別に把握して表示することとなっている。このことは、従来○○事業費と
いうように、様々な種類の費用が混入していたため、明瞭性が乏しかったが、それを改善するもの
である。
反面、各事業の費用がいくらかが明らかにならないため、内訳表示をすることが認められており、
内訳表示をせずに注記で示すこともできる。なお、共通経費の按分については、従事割合・使用割
合・建物面積比・職員数比など合理的な按分基準を用いる必要がある。
また、事務処理の簡便化・明瞭性の追及の観点から、貸借対照表の内訳表は求められておらず、
法人の任意で作成できるが、その他事業に固有の賅産で重要なものがある場合には、その賅産
状況を注記として記載することとしている。
(3)使途等が制約された寄付金等の扱い
寄付者等の意思により受入資産の使途等に制約が課されている場合には、原則として受け取った
年度に収益計上し、使途ごとに寄付金等の期首残高、増加額、減少額、期末残高を注記することに
なる。
なお、重要性が高い場合には、公益法人会計基準に沿って、指定正味財産の区分に計上し、
制約解除された場合には当該金額を一般正味財産に振り替えることとなる。
(4)助成金・補助金等の取扱い
返還義務のある助成金・補助金等については、当期受入額を収益として計上し、未使用額に
ついては前受けとして振り替える。この場合には、注記に当期受入額を当期増加額に、使用分
を当期減少額に記載し、前受け額を期末残高に記載する。
また、後払いの場合には未収計上し、その旨注記することとなる。なお、返還義務のない助成
金・補助金等については、(3)使途等が制約された寄付金等の扱いに準ずることとなる。
東京本部 笠田朋宏
2013,12,16, Monday
会社の成長には商品力が欠かせないという話を以前にしましたが、税理士事務所にとっての
商品力とは何でしょう。
商品のひとつとして決算書があります。決算書は作る者によって結構変わるものです。
作る側が誰に向けて作成しているのかでも変わります。
本来、お客様や株主に向けて作成するのですが、税務署向けに作成している税理士事務所も
少なくはありません。
ケースバイケースで考え方は変わるものの、せめて試算表くらいはお客様に向けて作成すべき
ではないでしょうか。
お客様にとって適正な損益を把握できる試算表のことをここで「月次決算書」と呼ぶことにします。
イメージとしてはいわゆる決算書に近い数字ものを毎月作成するようなものです。
違う言い方をすれば、精密度の高い月次試算表です。
月次決算書と言えば大そうなものに聞こえますが、いわゆる決算書ほど精密である必要はあり
ません。
当月の適正な期間損益把握が大まかに行うことが出来れば充分です。
では具体的にどのようにすればよいのでしょうか。大きくは以下の通りです。
☆ 発生主義で計上する。
☆ 在庫を計上する。
☆ 引当金の計上を行う。
☆ 税抜き経理を行う。
☆ 減価償却費を計上する。
☆ 仮勘定を使わない。
☆ 税金の未払計上を行う。
【 発生主義で計上する 】
売上、仕入、経費について当月に発生したものを売掛金、買掛金、未払費用等で計上します。
入金や支払いがあったときに損益を認識されている場合は、決算で大きく数字が変わってくる
ことがあるため、ご注意下さい。
月次決算では手間も考慮して、少額なものは計上しなくても問題がありません。
【 在庫を計上する 】
概算でもよいので、毎月在庫を計算します。例えば月末近くに100万円の仕入を行い売上は
翌月となった場合、100万円の在庫を計上しなければ、当月の損益は100万円違ってきます。
会社の規模により一定の基準を設けて実施すればスムーズに行えるでしょう。
【 引当金の計上を行う 】
賞与引当金、退職給与引当金、その他大きな支出が予想されるものを毎月引き当て計上し
ます。年に1度だけ賞与を支払うような会社であれば、賞与の支払い月だけが大きく経費が
増えてしまいます。
しかし賞与の支給は1年を通して徐々に発生していきますから、本来賞与の支給月以前にも
経費負担が発生しているため概算で計上します。
税務上認められないから計上しないというのは、税務署に向けて仕事をしているようなものです。
【 税抜経理を行う 】
税込み経理を行っていると、月々は消費税の納税分だけ利益が多く計上されてしまい、決算で
消費税の納税分だけ損益が変わることになります。
どうしても税込み経理が良い場合は、納税分だけ経費を見積もり計上しましょう。
【 減価償却費を計上する 】
当期の減価償却費がどれだけあるということを認識されている経営者の方は、実際多くないのが
実情です。
ということは、減価償却費分だけ経営者の方が思われている利益と決算書の利益に差が生じて
しまいます。減価償却費も考慮して損益を把握しましょう。
【 仮勘定を使わない 】
期中に問題があるような場合、とりあえず仮勘定(仮払金、立替金、仮受金など)で処理する場合
があります。
精算予定があるときは別として、出来る限り早い段階(原則として翌月)で問題解決を行いましょう。
【 税金の未払計上を行う 】
会社の利益は、税金を払ったあとの金額です。月次決算を行うことにより現段階でどのくらいの
納税が発生するということが把握できます。
それを未払計上することにより本当の損益の把握が可能となります。
以上7つの点について簡単に説明させていただきましたが、御社ではいくつ実施されていますか?
「そのようなことは当たり前にできている。」という経営者の方には申し訳ない話でしたが、もし
興味を持っていただいた方は、是非、当税理士法人優和の担当者にご相談下さい。
思っているほど手間は掛からないにも関わらず、大きな効果が期待できることでしょう。
京都本部 中村真紀