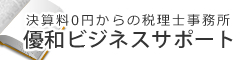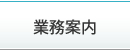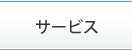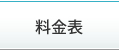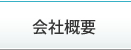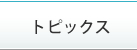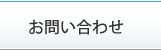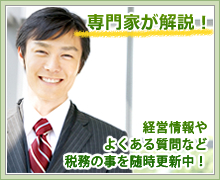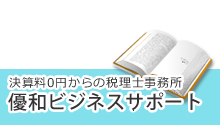遺留分権利者と合意し、所要の手続きを経た場合に遺留分算定で特別な計算が
できる制度です。
後継者が安定的に経営をしていくためには、生前贈与などににより自社株式や
事業用資産を集中的に継承させることが必要となります。
しかし、被相続人の事業を引き継ぐ後継者以外の相続人からの遺留分減殺請求
により、後継者が事業継続に必要な自社株式等を放出せざるを得なくなるときもあります。
このような問題に対処するため、経営承継円滑化法では遺留分に関する民法の特例
(遺留分特例制度)が規定されています。
■遺留分算定に係る特例
遺留分算定に係る特例とは以下のようなものです。
(1)除外合意
先代の経営者から後継者へ生前贈与した自社株式等について、遺留分算定の基礎
財産から除外することができます。
これにより、自社株式等に係る遺留分減殺請求を未然に防止することができるようになります。
(2)固定合意
遺留分算定基礎財産に算入する価格を合意時の時価に固定することができます。
これまでは、贈与後会社の業績を伸ばし会社の株式価値が増加した場合には、
株式価値を増加させた分まで遺留分算定の対象になってしまいましたが、固定合意により
後継者が株式価値上昇分を保持でき、経営意欲の阻害要因を排除することができます。
この特例を利用するには、いずれも推定相続人全員の合意により、書面で定めをする
必要があります。
また、その上で経済産業大臣の確認、及び家庭裁判所の許可を受けることが必要となります。
手続きの煩雑さからこの特例の利用は敬遠されがちではありますが、28年4月から
後継者が親族外のものでも対象となるよう拡充されましたので事業継承の解決策の
一つとして上手に利用していきたいものです。
茨城本部 香川
記事のカテゴリ:その他