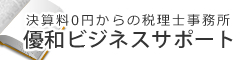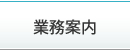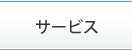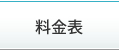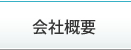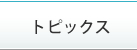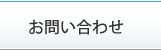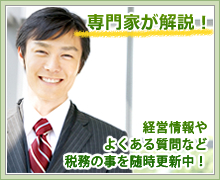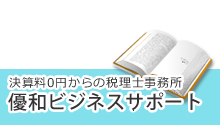雇用者への給与等の支給額を一定割合以上増加させる等の要件を満たした場合、
その増加額の10%を法人税額から控除できます(税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)。
従業員数を多く抱えている企業では、人件費の比重が高いことが想定できます。
そのため、毎年従業員の昇給等がある企業では、給与等の増加額のうち10%(税額の10%
(中小企業者等は20%)が上限)の税額控除は、節税のみならず、企業の資金繰り等を考慮しても、
影響の大きいものではないでしょうか。
(2)適用要件:次の①~③を全て満たすこと
①雇用者給与等増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上に
なっていること
この要件について、法人税の改正により、平成28年度では基準年度の4%以上(中小企業者等
では3%以上)に、平成29年度では基準年度の5%以上(中小企業者等では3%以上)になって
いることが必要となります。
②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額(前事業年度)以上であること
③平均給与等支給額が比較平均給与等支給額(前事業年度)を超えること
実務上、①②の計算は比較的容易に算出することができると考えられますが、③の計算は
少々複雑になっていると思います。
なぜなら、③の計算は①②の計算以外にも、前事業年度と適用年度の従業員の比較等も
必要になるからです。
例えば、前年度に在籍していた従業員が適用年度には全く在籍していなかった場合には、
前事業年度の平均給与等支給額からも控除することになります。このように、ある従業員は
比較の対象になるけれど、ある従業員は比較から対象外になるなど判別が必要になるので、
従業員数が過度に多くなった場合には実務上計算が煩雑になるのではないかと考えられます。
最後に、雇用拡大促進税制は、確かに計算が煩雑になる部分もあると考えられます。
しかし、毎期昇給等がある企業では、節税による恩恵は大きいものと考えられます。
そのため、企業は決算期に近づいたとき、適用要件を満たしているかを仮計算し、要件に
満たしていなければ、あといくら金額を増加させれば満たすのかを予測し、必要ならば
決算賞与で調整することも検討してみてはいかがでしょうか。
場合によっては、従業員に対する決算賞与よりも税額控除による節税効果の方が大きいことも
有ると考えられます。
そのようなことになれば、従業員のモチベーションも増加し、節税効果も得られるという一石二鳥の
成果が得られるかもしれません。
茨城本部 大河原 章憲
記事のカテゴリ:税務情報